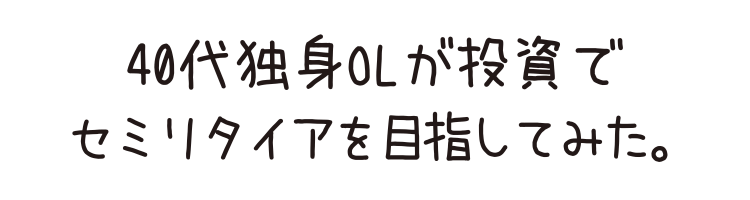「iDeCoはやめとけ!」「iDeCoはデメリットが多い」と言われます。
詳しく教えて!
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で運用して将来の老後資金を作る年金制度のこと。
とてもメリットが多い制度であることは間違いないですが、ネットでは「iDeCoはやめとけ」「iDeCoはデメリットが多い」「iDeCoは向いていない人がいる」という口コミが多いのも事実です。
そこで今回は、iDeCoがやめとけ&デメリットが多いと言われる理由を徹底解説!さらに向いている人と向いていない人の違いも整理してみました。
▼本記事の内容
iDeCoはやめとけ&デメリットが多いと言われる理由
iDeCoが向いていない人・おすすめできない人
iDeCoが向いている人・おすすめな人
iDeCoが向いていない職種や家計状況はある?
ご紹介内容はあくまで個人の見解と運用実績であり、正確性や安全性を保障するものではありません。また情報提供のみを目的としており、投資、法務、税務その他のアドバイスを意図しているわけでもありません。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。詳細はこちら
iDeCo(イデコ)とは
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で運用して将来の老後資金を作る年金制度のことです。
自分で運用して作る「年金」である
3つの「節税メリット」がある
自己破産しても没収されない
特徴を一つずつ見ていきましょう。
自分で運用して作る「年金」である
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、将来の老後資金を運用で増やしていく、自分でつくる年金制度です。
月々5,000円から積立可能で、将来もらえる年金が十分でない可能性が出てきた今、とても注目されています。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
=将来の老後資金を運用で増やしていく、自分でつくる年金制度
=運用の掛金が全額所得控除になるなど大きな節税メリットがある
=月々5,000円から積立可能

ありがたい制度だけど、「これからは自分の年金は自分で運用して作ってね」という裏のメッセージも感じるわ…笑
3つの「節税メリット」がある
iDeCoには、3つの節税メリットがあります。
➀掛金が所得控除になる
➁運用益が非課税になる
➂年金受取時も退職所得控除か公的年金等控除が受けられる

NISA制度はこのうちの➁の運用益の非課税しかメリットがないので、節税メリットはNISAよりiDeCoのほうが大きいです。
所得控除とは、掛金を所得から引いて税金がかかる課税所得を減らすことができる仕組みのこと。
また、受け取る時の公的年金等控除や退職所得控除も同じく、課税所得を減らすことができます。
所得控除
=所得から掛金を引いて課税額を減らすことができる
公的年金等控除
=年金として受け取る際に課税額を減らすことができる
退職所得控除
=一時金として受け取る際に課税額を減らすことができる

運用益が非課税になるのは、NISAと一緒です。
通常、株式投資や投資信託、不動産などで得られた運用益(配当金なども含む)には、約20%の税金がかかります。
税金20.315%
=所得税15%+復興特別所得税0.315%)+住民税5%
しかし、iDeCoではこの運用益は非課税になり、税金はかかりません。
自己破産しても没収されない

最後にもうひとつ、以外なメリットもご紹介しておきます。
実は、iDeCo(イデコ)で運用中の掛金は、自己破産しても没収されません。
iDeCo(イデコ)は確定拠出年金法という法律の下で運営され、運用中の財産は、税金の滞納処分以外では差し押さえができない「差押禁止財産」に分類されます。
そのため、60歳をすぎたら予定通り支給されます。
差押禁止財産
=生活に欠くことのできない家財道具や、給料および退職金請求権の4分の3のこと。自己破産しても没収することはできない。
参考:確定拠出年金法第32条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

万が一、なにかしらのアクシデントによって資産がなくなってしまっても、iDeCoで作った老後資金は確保しておくことができます。ちょっと保険的な要素もある制度ですよね…。
\イデコが気になる人は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/
iDeCoはやめとけ&デメリットが多いと言われる理由
iDeCoはやめとけ&デメリットが多いと言われる主な理由は、以下の通り。
原則60歳までお金を引き出せない
中途脱退はできるが、途中解約ができない
加入期間によっては60歳になっても受給できない
65歳以降は積立できない
価格変動リスクや元本割れリスクがある
手数料がかかる(自己負担)
節税というよりは、課税の繰り延べである
一つずつ見ていきましょう。
原則60歳までお金を引き出せない
個人型確定拠出年金(iDeCo)がやめとけと言われるいちばんの理由は、原則60歳までお金を引き出せないことです。

一度積み立ててしまった金額は、よほどのことがない限り引き出すことができません。このルールをデメリットに感じる人は多いみたい。でも…コレってメリットでもあるんです。
iDeCoで積み立てるお金の利用目的は、老後の生活資金です。
そのため、「60歳まで引き出せない」という制約があることで、途中で引き出せない環境が自然に作られ、老後の生活資金を用意するという目的を達成しやすくなります。
中途脱退はできるが、途中解約ができない
個人型確定拠出年金(iDeCo)は原則60歳までお金を引き出せないだけでなく、途中解約自体ができません。
ただし、いくつかの条件を満たした場合に「中途脱退」が認められています。
中途脱退=脱退が認められ、「脱退一時金」を受け取ることができる
iDeCo公式サイトには、条件が明確に書かれています。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、原則として、中途解約して払い戻しを受けることはできません。ただし、以下の1~7の支給要件をすべて満たす場合は、脱退一時金を受給することができます。
1.60歳未満であること
2.企業型確定拠出年金加入者でないこと
3.個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない者であること(国民年金保険料免除者や外国籍の海外居住者など)
4.日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
5.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
6.通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
7.最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること

えー。障害者になってしまったケースでも中途解約できないの?

その場合は「障害給付金」として非課税の給付金が受けられるよ。
| 給付種類 | 給付開始時期 | 受取方法 |
|---|---|---|
| 老齢給付金 | 60歳以降75歳まで | 一時金または年金 |
| 障害給付金 | 障害時 | 一時金または年金 |
| 死亡一時金 | 死亡時 | 一時金 |
iDeCoでは「生活が厳しいから積立をやめる」という選択はできませんが、障害や死亡の場合も給付金が受けられるため、脱退はできないですがある程度の補償がある制度になっています。
加入期間によっては60歳になっても受給できない
個人型確定拠出年金(iDeCo)はやめとけと言われやすい人は、50代以降の中年期の人です。
なぜならiDeCoは10年以上続けないと、60歳になっても受給できないというルールがあります。
中年期以降だと通算加入者期間が短いため、60歳になっても受給できないケースがあるからです。
| 通算加入者等期間 | 受取開始できる年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 満60歳 |
| 8年~10年未満 | 満61歳 |
| 6年~8年未満 | 満62歳 |
| 4年~6年未満 | 満63歳 |
| 2年~4年未満 | 満64歳 |
| 1ヶ月~2年未満 | 満65歳 |
例えば55歳から始めたとすると、65歳にならないと受け取りはできません。
65歳以降は積立できない
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、60歳からお金を引き出せますが、65歳以降は掛金の積立ができません。
中年期の55歳からiDeCoを始めた場合、65歳には積立ができなくなってしまうので、元本をそれ以上増やすことができません。
この場合、積立期間が短く、思っていた利益を上げられないという問題も起こりやすくなります。

利益が少なくなるだけならいいけど、タイミングが悪くて暴落してしまったら…ますます不満が増えそうです。
価格変動リスクや元本割れリスクがある
個人型確定拠出年金(iDeCo)はやめとけという人の中には、価格変動リスクや元本割れリスクを気にしている人もいます。
iDeCoを通じて運用をする時は、定期預金、保険、投資信託などの金融商品の中から、自分が好きなタイプの資産を選択することになります。
これらの金融商品は日々価格が変動し、時には元本割れになることもあります。
金融商品の種類によってそのリスクは異なりますが、リターンとリスクのバランスはほぼ同じで、リターンが大きい商品はリスクも大きくなり、リターンが小さい商品はリスクも小さくなります。
老後資金を準備するためのモノなのに、資産が減ってしまうのは大変と運用を避ける人は、iDeCOをやらないほうがいいと考えても不思議ではありません。
手数料がかかる(自己負担)

個人型確定拠出年金(iDeCo)はやめとけと言われる大きな理由に、手数料の存在もあります。
iDeCoに加入すると、いくつかの手数料が発生します。
まず金融機関に専用口座を開設する際の加入・移換時手数料がかかり、さらにその専用口座を維持するための管理費用が毎月かかります。
これらの手数料は、通常加入者の負担となりますが、元本保証型の商品を選ぶと手数料が運用利回りを上回ってしまうことも少なくありません。
| 国民年金基金連合会への新規加入&移換時手数料 | 2,829円(各社共通) |
| 加入後に毎月発生する手数料 | 66円or171円/月 |
| 給付手数料 | 440円(各社共通) |
| 還付手数料 | 1,488円 |

金融機関によっても異なりますが、なんだかんだで数千円はかかります。
最近は加入時手数料や口座管理手数料は無料の金融機関も増えていますが、この「無料」の範囲はあくまで金融機関が調整できるところだけ。
国民年金基金連合会への新規加入などにかかる費用は必ずかかるので、注意が必要です。

同じ国の制度であるNISAにはこれらの手数料がないため、どうしても大きなデメリットとして据える人が多いようです。手数料を払いたくない人は、NISAのほうがおすすめです。
節税というよりは、課税の繰り延べである
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、節税というよりは、課税の繰り延べであることもよく指摘されます。
①入金時:掛け金は全額所得控除
→そもそも住宅ローン控除などの税額控除を受けていて、納税額が0円になる人、所得が低くて納税額が少ない人はあまり関係がない
② 運用時:運用益は全額非課税
③ 出金時:受け取り時は一部非課税
→運用益は全額非課税でも、受け取り時には非課税枠を超えた分は全て課税対象
→受け取り時には自分で積み立てた元本(利益以外)も課税の対象になってしまう(株式投資や投資信託なら、普通は利益分しか課税されない)
→非課税枠内に年金収入とiDeCoの受取額が収まる人はそれほど多くない

本当に個人型確定拠出年金(iDeCo)がお得かどうかは、人によります。この判断が難しいので、「やめとけ」って言われることが多いんだよね…。
判断が難しい理由はかんたんです。正式な非課税枠は、以下の情報が確定しないと出せないから。
①いつ年金をもらうか?(65歳未満 OR 65歳以上)
②受け取る年金額はいくらか?(年金をもらう時までの年金加入実績によって変動)
正式な非課税枠は、企業年金連合会のホームページに掲載されている「公的年金等控除」で確認することができます。

またこの中の「受け取る年金額(A)」は、年金を受け取るときにならないと割り出せませんが、毎年はがきで届く「ねんきん定期便」に書かれた「これまでの加入実績に応じた年金額」から現状の金額を確認することはできます。

\イデコが気になる人には、この記事もおすすめ(*´▽`*)/
iDeCoが向いていない人・おすすめできない人
iDeCoが向いていない人・おすすめできない人は、以下の通り。
60歳より前の資産形成を優先する人
収入や納税額が少ない人
定期預金だけで運用する人
老後資金は確保済みの人
50代後半で運用できる年数が少ない人
一つずつ見てみましょう。
60歳より前の資産形成を優先する人
iDeCoは自分で積み立てる年金制度のため、原則60歳まで掛金が引き出せません。

前述したように、このルールはかなり厳しく、いくら途中で積立が辛くなってもやめられません。
自由度高く資金を移動させたい人や60歳より前にFIREしたい人、将来の夢や希望が何通りもあってまだ決めきれない人は、iDeCoで資産がロックされてしまうことに将来不満が出てくる可能性がありそうです。
iDeCoと同じ国の制度の中でも、NISAならいつでもお金を引き出すことができます。
運用益は非課税ですし、手数料もかからないのでiDeCoよりNISAのほうが気軽に始められるでしょう。
また、同じ理由から、生活費に余裕がなく、余剰金がない人もあまりおすすめできません。
iDeCoは最低5000円から積立できるので、始めやすい制度ではありますが、将来急にお金が必要になる可能性も考慮して、無理のない計画を前提にするのが望ましいと言えます。

まぁ、気楽に始められるのは間違いなくNISAだよね…笑
収入や納税額が少ない人
収入や納税額が少ない人は、iDeCoにメリットを感じることができないかもしれません。

そもそも納税額が少ない人は、iDeCoがデメリットしかないって思っても不思議じゃないかも…。
これは会社員やフリーランスとしてのお給料が少ないということだけではなく、他の減税措置を利用している人やパートナーの給与で暮らしている人も入ります。
・住宅ローン控除などの税額控除を受けている人
・納税額が0円になる人
・所得が低くて納税額が少ない人はあまり関係がない
iDeCoは始める時に手数料がかかります。

掛け金以外に口座管理手数料と運用管理費用が必要です。
収入が少ない場合は、大きな金額ではないにしても、手数料が不安要素となりハードルを上げてしまう可能性があります。
また、収入がないと、基本的には銀行預金を取り崩して運用に回す必要があることになりますから、iDeCoがプレッシャーになってしまうこともありえます。

iDeCoがデメリットに感じてしまうのは、この負担の大きさがあるのかもしれません。
定期預金だけで運用する人
また、iDeCoの運用先として、定期預金だけを予定している場合もあまりおすすめではありません。
定期預金は元本割れリスクがとても低い運用先です。
しかし超低金利時代の今、定期預金として運用してもほとんど資産を増やすことができません。
大手メガバンクの三菱UFJ銀行やみずほ銀行などでは約0.002%があたりまえですし、金利が高いといわれるネット銀行でも、楽天銀行で0.02%となっています。

100万円運用しても200円しか増えないなんて意味ある?…って思ってしまうのは普通だと思います。笑
特にiDeCoは手数料がかかるので、資産は微減していくことが予想できます。
50代後半で運用できる年数が少ない人
iDeCoは60歳から年金資産を受け取るには、最低10年の通算加入期間が必要です。
そのため、50代後半の方が始めた場合、60歳では年金を受け取ることができず、受給可能となる年齢が繰り下げられます。

これを知らない人が結構いて、不満の種になっているようです。
| 継続年数 | 受給開始年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上 | 61歳 |
| 6年以上 | 62歳 |
| 4年以上 | 63歳 |
| 2年以上 | 64歳 |
| 1月以上 | 65歳 |
iDeCoはNISAのように一気に大きなお金を入金することはできないのも、50代後半からはじめるデメリットのひとつ。
会社員の場合、毎月2.3万円ずつ積み立てたとしても、5年で138万円までしか入金できません。
2.3万円×12か月×5年=138万円
iDeCoの平均利回りである4.03%で運用したとしても、5年で14.6万円しか増えません。


14.6万円だってすごいけど…これで老後は安泰!…とはなりませんよね…笑
\まずは1000万円から貯めたいという人には、この記事がおすすめ(*´▽`*)/
iDeCoが向いている人・おすすめな人
iDeCo(イデコ)にはメリットもデメリットもありますので、自分の年金計画を建てる上で、加入が必要かどうか、じっくり検討することが必要です。
国民年金の第1号被保険者(自営業者等)の人
所得税をたくさん払っている人
資金に余裕がある人
年齢の若い人
一つずつ見てみましょう。
国民年金の第1号被保険者(自営業者等)の人
iDeCoはそもそも自営業者のための制度だという人がいるほど、自営業者向きの制度で、月額68,000円の最も大きい拠出枠を利用することができます。
この理由は、自営業者は会社員などが加入する、厚生年金に入ることができないからです。
厚生年金は死亡や障害などの保障が手厚く、老齢年金の額も自営業者の約3倍もらうことができますが、自営業者は厚生年金に入れない分、自分で年金の準備が必要なだめ、利用可能額が大きく設定されています。
iDeCoに拠出した額は、小規模企業共済等の枠で所得控除されますので、年間816,000円を控除でき、税金対策としても有効です。
所得税をたくさん払っている人
iDeCoはNISAと比べても税制優遇が大きな制度です。
所得税を払っている人であれば、上限枠までは所得控除できるので、iDeCoを使っても損はありません。
会社員の場合は1年で約5万円、自営業者の場合は1年で約16万円の税金の負担を軽減できます。
| 会社員 | 自営業 | 公務員 | |
|---|---|---|---|
| 支払った掛金 (年間支払額) | 月2万3,000円 (27万6,000円) | 月6万8,000円 (81万6,000円) | 月1万2,000円 (14万4,000円) |
| 1年間の税負担軽減額 | 5万5,200円 | 16万3,200円 | 2万8,800円 |
| 10年間の税負担軽減額 | 55万2,000円 | 163万2,000円 | 28万8,000円 |

逆に公務員の方がデメリットしかないと言われやすいのは、やっぱり使える枠が小さいのが大きな理由ですね。
資金に余裕がある人
iDeCoの加入がおすすめの人は、資金に余裕がある人です。
無理して将来の年金づくりをして、現在やりたいことを我慢するのは微妙かもしれません。若い時しかできないことを今するという選択も重要です。
入金時の節税効果はありますが、そもそも支払うべき税金が多くない場合、住宅ローンを組んでいる場合は、あまりメリットがないかもしれません。

「iDeCoはやめとけ!」「iDeCoはやばい」とおっしゃる方の真意は、やはり今現在の資金で精いっぱいなのに、将来にお金を先送りすることを心配されているケースが多そうですね。
年齢の若い人
iDeCoは突然大きな金額を掛金にすることはできず、コツコツと小さい額を積み立てる制度です。
そのため、時間があればあるほど資産を大きく構築できます。
例えば、今30歳の会社員と50歳の会社員が60歳の時に受け取る金額は、同じ条件で計算すると1000万円以上も違います。
| 最終積立金額 | 元本 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 今30歳の会社員 | 1596万円 | 828万円 | 768万円 |
| 今50歳の会社員 | 338万円 | 276万円 | 62万円 |

こうやって比べてみるとスゴイ違いだ…。シミュレーション条件は以下の通りです。
| 年間支払額 | 月2万3,000円(27万6,000円) |
| 年間利回り | 4% |
| 積立年数 | 今30歳の会社員:30年 今50歳の会社員:10年 |

30歳の場合のシミュレーションはこちら!


50歳の場合のシミュレーションはこちら!


iDeCoは若い人がやるなら、すごく意味のある制度なんです。
\FIREが気になる人には、この記事がおすすめ(*´▽`*)/
iDeCoが向いていない職種や家計状況はある?
iDeCoはどんな職種や家計状況であっても、上手く利用することができれば有益な制度です。
しかし、一部のケースでは向いていないと言われる理由があります。
公務員はやらないほうがいい?
会社員(サラリーマン)はやらないほうがいい?
専業主婦・主夫をしている人はやらないほうがいい?
住宅ローン控除を利用している人はやらないほうがいい?
一つずつ見てみましょう。
公務員はやらないほうがいい?
公務員はiDeCoをやらない方がいいと言われる理由は、拠出できる掛金の枠が少ないからです。
| 会社員 | 自営業 | 公務員 | |
|---|---|---|---|
| 支払った掛金 (年間支払額) | 月2万3,000円 (27万6,000円) | 月6万8,000円 (81万6,000円) | 月1万2,000円 (14万4,000円) |
| 1年間の税負担軽減額 | 5万5,200円 | 16万3,200円 | 2万8,800円 |
| 10年間の税負担軽減額 | 55万2,000円 | 163万2,000円 | 28万8,000円 |
昔から公務員はもらえる退職金が多く、iDeCoは必要ないとされていました。
そのため、現在はiDeCoの拠出限度額が少なく設定されています。
拠出限度額が少なければ少ないほど、運用できる範囲が小さく、年金を大きく増やすことは難しくなります。

公務員でも「やらないほうがいい」わけではないけど、「やっても自営業者に比べるとインパクトが少ない」というのはありそうです。
会社員(サラリーマン)はやらないほうがいい?
会社員(サラリーマン)はiDeCoをやらない方がいいと言われる理由は、公務員同様、自営業者に比べると拠出できる掛金の枠が少ないからです。
さらに言うと会社員の場合は、加入している企業年金によって企業型DCに加入していることも多く、すでにいくらかの拠出が会社を通して行われていることがあるようです。

サラリーマンの中には、企業型DCに加入しているからiDeCoはやらなくてもいいかなと思っている人も多いみたいですね。
会社員の場合、転職先の企業年金の導入有無によって、拠出額の上限が異なることもあり、正確な手続きを調べたり、対応したりすることにわずらわしさを感じることも多く、やらないほうがいいというよりは、やると大変という認識の方が多いようです。

たしかに転職を繰り返すタイプの人は、なかなか大変かも…。
専業主婦・主夫をしている人はやらないほうがいい?
前述したようにiDeCoは所得がある方にとっては、所得控除などのメリットがありますが、所得がない方にとってはメリットの一部が享受できない問題があります。
もちろん運用中に発生した利益が非課税になる、受け取る時に退職所得控除や公的年金等控除を使えるというメリットはあるものの、それならばいったんは自由度が高く、理解しやすいNISAをはじめて、iDeCoは様子見でOKと考える人も多いようです。

iDeCoのほうが人を選ぶ制度だと言えそうです。
住宅ローン控除を利用している人はやらないほうがいい?
住宅ローン控除を利用している人についても、専業主婦・主夫の方と同じく、所得控除などのメリットが受けにくいという問題があります。
そのため専業主婦・主夫の方と同じく、まずはNISAからはじめ、余裕があればiDeCoの併用も検討するのがおすすめです。
\まずは1000万円から貯めたいという人には、この記事がおすすめ(*´▽`*)/
iDeCo(イデコ)のよくある質問Q&A
ここからは、iDeCo(イデコ)のよくある質問について整理してみたいと思います。
iDeCoとNISAはどっちがおすすめ?
iDeCoとNISAは全く目的が違う投資方法です。
iDeCo:個人で毎月お金を拠出する年金制度
NISA:長期安定投資のための非課税制度
どちらも運用して得られた利益が非課税になるという意味では共通していますが、NISAは特に老後を意識した制度ではなく、5年から20年程度を見据えて運用するための制度です。(使用する必要がなければ、そのまま長期運用が理想です。)
ロールオーバーなどの延長制度もありますが、年金を目的とするiDeCoとはそもそも目的が異なります。
通常の公的年金以外に個人年金の準備をしたい方はiDeCoがおすすめで、5~20年の長期運用投資が目的の場合はNISAがおすすめです。
企業型DC加入済みの場合、iDeCoはいらない?
勤め先である企業が企業年金規約で企業型DCとiDeCoの併用を認めていれば、企業型DC加入済みでも、個人型確定拠出年金(iDeCo)に入ることができます。
しかし、認めていない場合は、そもそも加入ができません。
今後ますます少子化が進み、年金制度に不安があることから、制度の改正も進んでいます。
2022年10月1日からは、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件が緩和され、規約の定めがなくても、iDeCoに原則加入できるようになる予定です。そうなると、すべての会社員がiDeCoに加入できるようになります。
【2022年10月1日以降のルール】
①すべての会社員がiDeCoに加入できる
②企業型DC加入者がiDeCoと併用する場合の掛金の上限は、月2万円
③企業型DC加入者は、企業型DCに個人で掛金を上乗せする「マッチング拠出」か、企業型DCとは別にiDeCoに加入するかを選択できるようになる
国としては、個人が老後資金を自分で準備できるようにサポートする制度をどんどんすすめているので、もしかしたら今後もう少しお得になるかもしれません。
これからの制度改正にも注意したいところです。
iDeCoの2022年度法改正!メリット・デメリットは変わった?
2022年の法改正によって、iDeCoがさらに加入しやすくなりました。
・加入年齢制限が5歳分長くなった
・企業型確定拠出年金加入者でも入りやすくなった
| 法改正前 | 法改正後 | |
|---|---|---|
| 受け取り開始時期 | 60歳~70歳 | 60歳~75歳 |
| 加入可能年齢 | 60歳未満 | 65歳未満 |
| 企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入の条件緩和 | 労使合意に基づく規約の定めがあり、事業主掛金の上限の引下げに対応している企業の従業員のみ | 労使合意の規約や事業主掛金の上限の引下げがなくてもOK |
\まずは節約からはじめたいという人には、この記事がおすすめ(*´▽`*)/
【合わせて読みたい】
お金を使わない人の6つの心理的特徴・共通点を解説!お金を貯める習慣を紹介
体験談!筆者がiDeCoの加入をしていない理由
わたしは、今後はまだわかりませんが、現状、iDeCoの加入はしていません。
その理由としては、2つあります。
①すでに企業型DCには加入済みである(事業主掛金:24,000円/月のみ)
②個人年金代わりの資産をすでに積立積みである
【企業型DCの運用実績】
資産残高:3,222,336円
拠出金累計:2,544,000円
損益:678,336円
損益率:26.7%
運用利回り:5.4%
将来の年金はもちろん大事ですが、今しかできないことに使うお金もとても大事なので、今のところは将来のためのお金は上記2点で準備し、他は今現在に投資していく予定です。
しかし、国がiDeCo(イデコ)に力を入れて、制度改善を積極的に行っていると感じているので、またお得なことが増えたり、自分の状況が変わったら、今後加入する可能性もあると思います。

ルールが変わって心配な点が減ると、「iDeCoはやめとけ!」「iDeCoはやばい」とおっしゃる方も減ってくるかもしれませんね。
\まずは1000万円から貯めたいという人には、この記事がおすすめ(*´▽`*)/
まとめ:iDeCoはやめとけ&デメリットが多いと言われる理由と注意点
今回は、iDeCo(イデコ)について、まとめてみました。
iDeCo(イデコ)は、私的年金制度のひとつで、今国がとても力をいれて発展させている制度です。
しかし、さまざまな理由から「iDeCoはやめとけ!」「iDeCoはやばい」とおっしゃる方がいることも事実です。
iDeCo(イデコ)はやめとけ!と言われる理由は以下のとおり。
原則60歳までお金を引き出せない
中途脱退はできるが、途中解約ができない
加入期間によっては60歳になっても受給できない
65歳以降は積立できない
価格変動リスクや元本割れリスクがある
手数料がかかる(自己負担)
節税というよりは、課税の繰り延べである
iDeCo(イデコ)は、運用中は課税されないものの、将来的には非課税枠に収まらず、非課税のメリットがあまりない可能性があります。
また、一度はじめてしまうと60歳までやめられないことから、警戒する方も多くなっています。
積立をやめることはできますが、運用はやめられないので、積立をやめたとしても手数料はかかり続けます。
若いうちから老後の年金の準備をしておくことは大事なことですが、そのために今を犠牲にするのはあまりよい選択とは言えません。
自分が大事なことをもう一度振り返り、自分にとって後悔のないお金の使い方を考えてみてください。
それでは今日もまめまめたのしい1日を。
\イデコが気になる人は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/