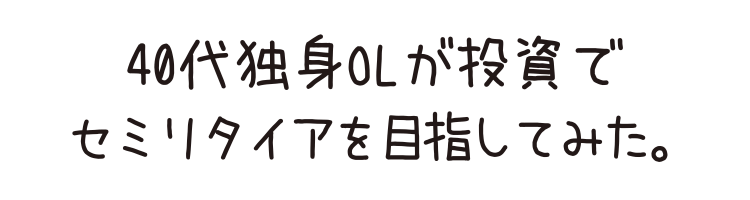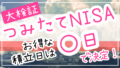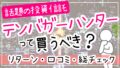ファンドラップはひどいってホント?
金融庁が注意喚起をするのはなんで?
ファンドラップは、金融機関が顧客の代わりに資産の運用や管理を行う金融商品のひとつ。
プロに投資を任せることができる一方で、金融庁も注意喚起するほどリスクも気になる商品です。
そのせいか、ネットでは「ファンドラップはひどい」「ファンドラップはやらないほうがいい」など悪評がたつことも。
そこで今回は、ファンドラップの実態を徹底考察!
投資歴15年のOL投資家がファンドラップを選ばない理由や根拠も整理してみました。
▼本記事の内容
ファンドラップはひどいってホント?
金融庁が注意喚起をするのはなんで?
ご紹介内容はあくまで個人の見解と運用実績であり、正確性や安全性を保障するものではありません。また情報提供のみを目的としており、投資、法務、税務その他のアドバイスを意図しているわけでもありません。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。詳細はこちら
ファンドラップとは?
まずは「ファンドラップ」という言葉の意味から整理してみましょう。
ファンドラップの意味
ファンドラップとは、金融機関が顧客の代わりに資産の運用や管理を行う金融商品です。
ファンドラップ
=金融機関が顧客の代わりに資産の運用や管理を行う金融商品
=Fund(投資信託)+Wrap(包む)

詳しく見てみましょう!
ファンドラップの概要
ファンドラップは、金融会社との間に「投資一任契約」を結び、金融会社とともに投資方針を決め、運用していく資産運用商品のことを指します。
投資一任契約
=投資運用業者が投資家から投資判断の全部または一部を一任される契約
=その投資判断に基づき投資を行うための権限を委託される契約
顧客の投資目的や期間に応じて、金融会社が投資方針を決めるため、顧客は専門家に資産運用をおまかせすることができます。

お金のことを考えるのがニガテな人にとっては、とても便利なサービスです。
日本投資顧問業協会が四半期ベースでまとめている「契約資産状況」によると、2023年3月末のファンドラップ口座残高および件数は過去最高値を記録。
残高:14兆6472億円
件数:152万1367件

引用:ラップ契約残高が過去最高 一部で販売鈍化も|日本経済新聞

「ファンドラップはひどい」という口コミがあるものの、これだけ増えているってことは…。普通に利便性が高いと感じている人もいるってことかなぁ…
ファンドラップの仕組み
取引する金融機関と投資一任契約を結ぶと、金融機関は顧客の資産状況や計画をヒアリングしながら、顧客の最適なポートフォリオを検討します。

そのためプロの視点で、自分に合った最適な資産配分を見つけてもらうことができます。
また、通常は運用しながら自分で調整していくポートフォリオですが、運用中の配分の見直しも相談しながら金融会社が行います。
ファンドラップと投資信託の違い

ファンドラップって、投資信託と同じじゃない?
プロにどの投資信託を買ったらいいか、アドバイスがもらえるだけの違い?

うーん…。そう思っていると危険かも…。メリットだけじゃなくて、デメリットもあるよ。
ファンドラップは、「ファンド(=投資信託)」とついているように、結局は投資信託を購入します。
でも、以下の点が大きく異なります。
| ファンドラップ | 投資信託 | |
|---|---|---|
| 商品ラインナップの自由度 | 少ない あらかじめ決められた ファンドの中から選ぶ | 多い 世の中にあるファンドなら どれでも購入できる |
| サービスの質 | 金融機関の営業担当者が 定期的に運用報告をしてくれる (質問機会あり) | 運用成績については 自分で常に追う必要がある (質問機会なし) |
| コスト(費用) | 通常の手数料 (購入手数料+信託報酬など) に投資一任報酬が追加発生する | 通常の手数料 (購入手数料+信託報酬など) のみ |

自分で資産運用するつもりがあるなら、わざわざ高いコストを払ってファンドラップを買う必要はないですが、自分で運用したくない人にとっては便利なサービスになります。
ファンドラップとヘッジファンドの違い
ファンドラップとごっちゃになりがちなのが、ヘッジファンドです。

同じ「ファンド」がついていることから、投資信託に関連するのはわかるけど…ごっちゃになりやすいみたい。
ヘッジファンドは、金融会社のプロのファンドマネージャーに運用をおまかせする点は、ファンドラップと同じです。
でも、その目的は市場の下落を避けること。
プロだからこそできる、先物取引や信用取引などを積極的に活用して、市場が上がっても下がっても、利益を生むことを目指します。
ヘッジファンド
=さまざまな取引手法を駆使して市場が上がっても下がっても利益を追求することを目的にして金融会社が組む投資信託のこと
=Hedge(避ける)+Fund(投資信託)
最低投資金額は、ファンドラップよりもさらに高額の1000万円程度からになりますが、富裕層の一つの選択肢としてとても人気があります。
\NISAが気になる方は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/
ファンドラップがひどい!?5つの理由【金融庁も注意】
ファンドラップは、個人投資家にとってバランスがよい商品とは言いずらいな…と言うのが投資歴15年の私の素直な感想です。
ルールがわかりにくいのもあって、ちゃんと納得してから買う人も多くないことから、「ファンドラップはひどい」「ファンドラップを買って後悔した」などと、SNSなどで不満が露呈するのも納得できます。
ファンドラップがひどいと言われる理由は、主に次の5つ。
運用パターンは数種類!オーダーメイドではないから
本質は手数料ビジネス!高く、二重で取られるから
最低投資金額が300万円以上の富裕層ビジネスだから
高い手数料を払っても利回りの実績が40%以上劣るから
約5割が自社系列商品で選定方法に偏りがあるから
ひとつづつ見ていきましょう。
運用パターンは数種類!オーダーメイドではないから
ファンドラップがひどいと言われるいちばんの理由は、ひとりひとりの個人投資家に合わせたオーダーメイドの投資信託を組んでくれるように見えて、実はオーダーメイドではないからです。

ヒアリングの結果をおすすめしてもらえるので、オーダーメイドだと思ってしまう人も多いよね。
多くの金融会社では、顧客のリスク許容度を「安定重視」「バランス」「成長重視」などのグループに分け、そこからヒアリング内容に合いそうな投資信託を選択するだけ。
これなら自分で投資信託の商品概要を見るだけでできてしまう人もいるので、手数料を払わないといけない分、損をした気持ちになる人も多いでしょう。
また、選定される商品があらかじめ決まっているので、選択の自由の幅が狭く、むしろ自分で選んだほうがいろんな商品が選べて良いと考える人もいそうです。

どちらかというと本当に投資に興味がないか、忙しくて一切調べる時間が持てない人向けで、多少自分で調べることができる人は不満につながりやすい印象があります。
大和証券のファンドラップを見てみましょう。
| ダイワファンドラップ | ダイワファンドラップ プレミアム | |
|---|---|---|
| 契約金額 | 300万円以上 | 3000万円以上 |
| リスク許容度 | 5種類から選択 | 7種類から選択 |
| 対象ファンド | 計10本から選択可能 | 計42本から選択可能 (最大3銘柄選択可能) |
| 手数料 | 資産評価額(契約金額)およびリスク水準に応じた料率 | 資産評価額(契約金額)およびリスク水準に応じた料率 |
選べる投資信託は予算によって異なりますが、300万円規模の投資だと10本から1つ選ぶスタイルが一般的です。

うーん…だとしたら、普通に自分で「オルカンかS&P500連動型の商品を買う」のほうが手数料分お得かも…。
3000万円以上投資するつもりであれば選択の幅は広がりますが、その分手数料も値上がりするため、証券会社のファンドマネージャーとのコミュニケーションに価値を持たない人は、あまりメリットを感じられない可能性があります。
私の知り合いには、ファンドマネージャーと定期的に話して勉強の機会を持ちたいという意味で、ファンドラップを購入している人がいます。
そのメリットを感じられる人にとっては、よいサービスだと感じられる可能性がありそうですが、単純に資産運用だけの目的だと、「オーダーメイドだと思ったのに」「ゼロからプロが運用プランを組んでくれると思ったのに」と、不満につながる可能性も高いです。

人によってメリットを感じる場所は違うので、サービスの内容をちゃんと理解してから契約することが大事!
本質は手数料ビジネス!高く、二重で取られるから
ファンドラップがひどいと言われがちなのは、何と言っても「手数料が高い」という特徴にあると思います。
そもそもファンドラップのサービスの中に含まれる投資信託は、特別なものではなく、個人が直接購入する投資信託と同じです。
そのため、投資信託を購入&保有するとかかる通常の手数料は、ファンドラップでも同じようにかかります。
ファンドラップの場合、さらに個々の相談料として手数料が乗ってくるわけですから、普通の投資信託よりも高額な手数料が請求されるのは、あたりまえだとも言えるでしょう。

金融会社が個人投資家と1対1で対応する時点で人件費がかかるもんね…。
金融庁の調査によると、ファンドラップの平均年間手数料は2.2%。
個人で購入する場合は購入時に平均3%の販売手数料はかかりますが、その後の平均年間手数料は1.5%です。
4年間継続投資を続けると、ファンドラップよりも個人購入のほうがコストが安くなり、さらに10年間継続投資を続けると、年間4%も手数料が変わってくることがわかります。

【個人で投資信託を購入した場合】
3%の購入料金+1.5%の保有料金(信託報酬+信託財産留保額)=初年度4.5%+年間1.5%
【ファンドラップを利用した場合】
2.2%のファンドラップ料金(投資一任報酬)=年間2.2%
最近はNISAなどの新しい制度が生まれ、さらに個人投資が一般的になったことで、個人で投資信託を購入する際の手数料はどんどん低くなっています。

個人投資家に人気のemaxis slim 全世界株式(オール・カントリー)の信託報酬は、なんと0.05775%です。ますます「ファンドラップはひどい(=手数料が高すぎる)」って思っちゃうよね。
日本の金融機関が提供するファンドラップは、もともと決められた仕組みに沿って商品を提供するだけのため、その付加価値についてあまり研究がされていません。
しかし、投資大国のアメリカの場合は、金融機関が提供する付加価値についての研究がとても多くなっています。
日本の金融機関よりも手数料は多くなりますが、その分きちんと「コンサルティング」をしているケースが多いようです。
アセット・アロケーションやリバランスよりも、投資行動のコーチングや税金対策などの実務的なアドバイスも行うため、とても有用です。


どうせ手数料がかかるなら、多少高くてもコンサルティングを受けたいかも…!
最低投資金額が300万円以上の富裕層ビジネスだから
ファンドラップがひどいと考える人の一部には、いわゆる「富裕層だけの特別扱いビジネスだから」という理由もあるようです。
一般的なファンドラップの最低購入額は、300万円から。
| ファンドラップ名(金融機関名) | 最低購入額 |
|---|---|
| 野村ファンドラップ(野村證券) | 500万円以上 |
| ダイワファンドラップ(大和証券) | 300万円以上 |
| SMBCファンドラップ(三井住友銀行) | 300万円以上 |
| りそなファンドラップ(りそな銀行) | 300万円以上 |
| FIRST STEP(みずほ銀行) | 500万円以上 |
| ゆうちょファンドラップ(ゆうちょ銀行) | 300万円以上 |
NISAなどの制度を活用して自分で投資信託を買う場合は100円からできるのに、300万円を一気に預けないとそもそもサービスを利用できないことに、一種の違和感を覚える人がいます。
「家計の金融行動に関する世論調査」によると、30代単身世帯の金融資産の中央値は56万円です。
また、二人以上世帯の金融資産の中央値は238万円。
30代の半数はファンドラップサービスを利用すること自体ができません。
| 30代の金融資産 | 単身世帯 | 二人以上世帯 |
|---|---|---|
| 金融資産平均額 | 606万円 | 752万円 |
| 金融資産中央値 | 56万円 | 238万円 |
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/tanshin/2021/21bunruit001.html
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/futari2021-/2021/21bunruif001.html
高い手数料を払っても利回りの実績が40%以上劣るから

高い手数料を払っても利回りがいいならやってみたい…

それが…実績値を見ると利回りも微妙なんだよね…笑
ヘッジファンドダイレクト株式会社が発表したファンドラップ型サービスの「手数料控除後リターン」ランキングによると、いちばん利回りの成績がよかったSMBCファンドラップでも、年率8%。
中には投資一任手数料を引くとマイナスになってしまうファンドラップも存在します。
| 順位 | サービス名 | ネットリターン |
|---|---|---|
| 1 | SMBCファンドラップ | 8.068% |
| 2 | 三井住友信託ファンドラップ | 4.688% |
| 3 | 野村ファンドラップ | 4.569% |
| 4 | ダイワファンドラップ | 2.855% |
| 5 | 日興ファンドラップ | -2.176% |
| 6 | みずほファンドラップ | -3.440% |
一方、個人投資家が自分で投資信託を購入した場合と比べてみましょう。
実際に私が個人投資家として購入している人気の投資信託「emaxis slim 米国株式(s&p500)」のトータルリターンは以下のとおり。
| 1ヶ月 | +4.26% |
| 3ヶ月 | +17.62% |
| 6ヶ月 | +24.49% |
| 1年 | +49.00% |
| 2年 | +20.46% |
| 3年 | +23.55% |
| 5年 | +22.19% |
| 10年 | — |
また、運用報告書によると総経費率(年率)は0.11%です。
は0.11%.png?resize=864%2C395&ssl=1)
引用:運用報告書|emaxis slim 米国株式(s&p500)
ここ1年間のネットリターンを計算してみると、48.89%になります。
49.00%-0.11%=48.89%
一方、人気のファンドラップ「三井住友信託ファンドラップ」の月次レポート(2024年3月号)を見てみると、積極的に攻めた場合の年率リターンは6.8%。
.png?resize=969%2C307&ssl=1)
引用:「三井住友信託ファンドラップ」の月次レポート(2024年3月号)
ここから投資顧問報酬の1.760%を引くと5.04%です。
6.8%-1.760%=5.04%
(1)直接ご負担いただく費用
投資顧問報酬には、固定報酬と成功報酬があり、固定報酬はお客さまの運用資産の時価評価額に対して最大年率1.760%を乗じた額、成功報酬は運用成果の16.5%をお支払いいただきます。
個人投資とファンドラップの利益率を比べてみると、40%以上も違いが出てしまいました。
個人投資の利益率 48.89%
ファンドラップの利益率 5.04%
もちろん暴落時のリスクなど細かい点を見れば、分散投資による安定運用が前提のファンドラップは暴落に強いとは思われます。
でも、それでも利回りの実績が低いことは契約前に知っておく必要があります。
金融庁の調査によると、「コストが高いファンドラップほど、パフォーマンスが劣る傾向がある」ことがわかっていて、これには金融庁も注意喚起をしています。
コスト控除後の5年間のシャープレシオを見ると、バランス型ファンドに劣るファンドラップが依然として多い。コストが高いファンドラップほど、パフォーマンスが劣る傾向がある。(中略)高コストで安全資産の組入れ比率の高いファンドラップについては、真に顧客利益に資するものか、商品性についての再考が求められる。
約5割が自社系列商品で選定方法に偏りがあるから
ファンドラップは、金融会社に全体的におまかせする分散投資法としてはメリットもありますが、金融会社もボランティアでサービス提供をしているわけではないため、自社にメリットがある商品を売ろうとします。

商売なので、しょうがないと言えばしょうがないですよね。
金融庁は「平成27事務年度金融レポート」の中で、ファンドラップは平均5割の投資信託が系列の商品であることを指摘。
顧客の安定的な資産形成のための業務が行われているとは必ずしも言えないとし、金融機関の利益よりも顧客利益を優先させることの大切さを指摘しています。
一方、対象の証券会社や信託銀行が提供しているファンドラップについて、運用対象の投資信託の中身を見ると、系列の投資運用業者が設定する投資信託が平均で5割前後を占めており、中には7割近くに達するものもある。

7割も?!ほぼ自社系列商品を売るためのサービスになっちゃってる…
なぜ金融機関はファンドラップに力を入れるのか?
金融機関がファンドラップに力を入れる理由は、金融機関側の利益率が高い商品だからです。
金融庁が指摘するように、アドバイスの中に自社および自社系列の商品を多めに盛り込むことで、自社の利益率が高い商品を自然な形でおすすめすることが可能なだけでなく、追加で手数料ももらえます。
特にファンドラップを契約する顧客は、自分の資産運用戦略を金融会社に任したい人であるため、金融商品に明るくない人が多いことが予想できます。
そうなるとますます、金融機関側の誘導通りに購入してしまう可能性が高く、金融機関にとって都合の良い商品になってしまっているのです。

ファンドラップがひどいと言われがちなのは、金融機関と商品購入者の利害が一致しないため、どうしても情報弱者である投資家の利益の最大化が難しい点に問題がありそうです。
\NISAが気になる方は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/
「ファンドラップはひどい」に関するよくある質問

「ファンドラップはひどい」に関するよくある質問を集めました!
ファンドラップの解約タイミングは?
ファンドラップをすでに契約していたとしたら、きちんと手数料にあった利益が出ているか、検討することが必要です。
費用に見合わない利益しか出ていないと思うのであれば、すぐに解約を申し出るのが賢明です。
2024年からは新NISAも始まり、自分で資産運用をするのが当たり前の時代に突入しています。
お金のことを考えるのが苦痛で仕方がない人でない限りは、まずは自分で投資信託を買ってみて、自分のリスク許容度を確認しながら投資を続けていきましょう。
自分で資産に関わる決断をする自信がない人は、ファンドラップを契約するのではなく、販売商品がないファイナンシャルプランナーなどに一度相談してみるのもひとつの手です。
ファンドラップの契約残高が伸びている理由は?
ファンドラップの契約残高は前述したように増加傾向にあります。
これには、いくつかの理由があります。
➀投資に興味を持つ人が増えている
➁金融会社がファンドラップ営業に力を入れている
2024年の新NISA導入により、資産運用や投資に興味を持つ人が増えています。
ファンドラップに関わらず、金融商品の販売数は増えていて、今後も増えていくことが予想されます。
また、金融会社側も顧客からの相談があった場合にファンドラップをおすすめするケースが多いことが考えられます。
実際に商品の利益率はそこまで高くありませんが、金融会社側の利益率が高い商品であるため、どうしても主力商品として利用されるケースが多くなっているようです。

私も大昔に窓口に行くと、ファンドラップをおすすめされました。投資初心者ほど全部おまかせできるファンドラップに魅力を感じがちなのかも…。
ファンドラップでNISAは利用できますか?
NISAの適応商品の中にファンドラップは含まれていません。
NISAはそもそものコンセプトとして、国民ひとりひとりが自立して将来の資産形成を行うことを目的とした制度です。
そのため金融会社に依存した形になりやすいファンドラップは、対象範囲外になります。
ファンドラップとヘッジファンドはどっちがおすすめ?
利益を追求したいならヘッジファンドがおすすめです。
前述したようにヘッジファンドは、市場の相場に関わらず利益を追求することを目的にしています。
ヘッジファンド
=さまざまな取引手法を駆使して市場が上がっても下がっても利益を追求することを目的にして金融会社が組む投資信託のこと
=Hedge(避ける)+Fund(投資信託)
プロのファンドマネージャーの信用取引や先物取引などのテクニックで、下落相場でも資産を守るべく動いてもらえます。
また、ファンドラップとは違い、成果報酬としてファンドマネージャーに支払う料金もあることから、ファンドマネージャーと消費者である個人投資家の利害が一致しやすく、金融会社だけが儲かるような仕組みにはなりにくいのもおすすめの理由です。
どちらにしろ、まずは個人投資家自身が最低限の金融知識をつけることが優先なので、まずは自分で運用してみることが大事ですが、ゆくゆく大きく育った資産をより安全に投資したいという希望が出てきた時は、ヘッジファンドの利用を検討してみてもよいかもしれません。
主なファンドラップと評判
ここからは主なファンドラップとTwitter上の評判をご紹介しましょう。
SMBCファンドラップ(三井住友銀行)
提供:三井住友銀行
最低投資金額:300万円以上
手数料:「固定報酬型」と「成功報酬併用型」から選べる
MUFGファンドラップ(三菱UFJ銀行)
提供:三菱UFJ銀行
最低投資金額:500万円以上
手数料:「固定報酬型」と「成功報酬併用型」から選べる
楽ラップ(楽天証券)
提供:楽天証券
最低投資金額:1万円以上
手数料:「固定報酬型」と「成功報酬併用型」から選べる
\NISAが気になる方は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/
まとめ:ファンドラップはひどい?富裕層の私がやらない理由を解説
ファンドラップはひどいと言われてしまう理由は、以下のとおり。
運用パターンは数種類!オーダーメイドではないから
本質は手数料ビジネス!高く、二重で取られるから
最低投資金額が300万円以上の富裕層ビジネスだから
高い手数料を払っても利回りの実績が40%以上劣るから
約5割が自社系列商品で選定方法に偏りがあるから
金融庁も警笛を鳴らすほど、ファンドラップはリスクが高い商品であり、利用者のスキルが問われます。
私も投資初心者のころは窓口でおすすめされたことがありますが、自分の資産をひとまかせにしてしまうことに違和感を感じ、いったん保留に。
調べたところ、やはり利益率とコストが見合ってないように感じて、契約をすることはやめました。
もちろんファンドマネージャーと定期的かつ強制的に話す機会を持てるのは良いことですが、普通にこれから投資を始める方なら、まずは自分で調べて自分で投資信託を買ってみるところから始めてみるほうが、学びは大きいと思います。
ファンドラップの利用を考えるのは、ある程度投資知識がついてからでも遅くはありません。
それでは今日もまめまめたのしい一日を。
\株配当金生活が気になる方は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/