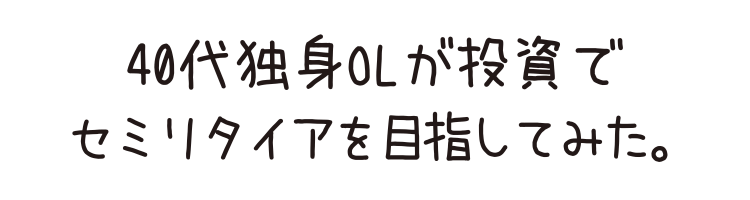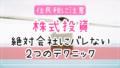財形貯蓄はやめたほうがいいってほんと?
「オワコンだ」「意味ない」ってどういうこと?
会社で勝手に加入させられているけど、大丈夫かな。デメリットが知りたい…
今回は、こんな疑問にお答えします。
▼本記事の内容
・財形貯蓄制度とは?
・財形貯蓄制度のメリットとデメリット
・財形貯蓄制度よりおすすめの資産運用方法とは?
昭和のエリートサラリーマンに大人気だった「財形貯蓄制度」。
ここ数年は「ニーズが少ない」などの理由から、導入する企業が激減しています。
財形貯蓄制度は、なぜ「意味ない」「やめたほうがいい」と言われはじめたのでしょうか?
今回は、そんな財形貯蓄制度について、徹底解説!
やめたほうがいいと言われる理由やメリット、デメリットを整理してみました。
ご紹介内容はあくまで個人の見解と運用実績であり、正確性や安全性を保障するものではありません。また情報提供のみを目的としており、投資、法務、税務その他のアドバイスを意図しているわけでもありません。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。詳細はこちら
財形貯蓄制度とは?3つの種類をわかりやすく解説
財形貯蓄制度は、働く人の財産形成を国と事業主が支援する制度として、昭和46(1971)年に生まれました。
財形貯蓄制度の定義
財形貯蓄制度の種類
減っていく財形貯蓄制度の導入率
一つずつ見ていきましょう。
財形貯蓄制度の定義
財形貯蓄制度とは、正式名称を「勤労者財産形成貯蓄制度」と言います。
財形貯蓄制度
=給与天引きによって自動的に積み立てられる貯蓄制度
=厚生労働省が行う「勤労者財産形成促進制度」に含まれる制度のひとつ
=勤労者財産形成促進法に定められている
働く人が自分の資産を計画的に作っていくことを目的に作られた制度で、給与天引きによって自動的に貯蓄ができる仕組みになっています。
勤務先が財形貯蓄制度を利用していれば、従業員はこの制度を利用して資産を築くことができます。


持っているお金は全部その場で使ってしまう散財タイプのあなた!
あなたにはぴったりの制度です(*´▽`*)
\枝豆の資産管理方法が気になる人は、こちらの記事もおすすめです(*´▽`*)/
【合わせて読みたい】
失敗しない貯金の仕方!5000万円貯めたわたしの口座の分け方と具体的な3つの手順
財形貯蓄制度の種類
財形貯蓄制度には、積立金の使い道(用途)によって3つの種類があります。
| 一般財形貯蓄 | 財形住宅貯蓄 | 財形年金貯蓄 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自由 | 住宅資金 | 老後資金や年金 |
| 加入条件 | 勤労者 | 満55歳未満の勤労者 | 満55歳未満の勤労者 |
| 積立期間 | 3年以上 | 5年以上 | 5年以上 |
| 税金の優遇制度 | なし | 550万円まで非課税 | 貯蓄型は550万円 保険型385万円まで 非課税 |

一つずつみていきましょう!
一般財形貯蓄
一般財形貯蓄は、自由に使える資金を作るための貯蓄制度です。
一般財形貯蓄
=用途・目的は自由、契約時の年齢制限なし
=事業主を通じて、定期的に賃金から天引きされる形で貯蓄する制度
特に税制の優遇などはなく、単純に給与天引きでお金が貯蓄用にプールされていきます。
一般財形貯蓄制度では、原則3年以上積立を続ける必要がありますが、1年経過後には自由に払い出しすることができます。
病気やケガ、結婚や出産など、突然お金が必要になった時に自由に使うことができるお金です。

最近は自分で資産管理をして投資をする人も増えているので、ちょっと昭和っぽい気がするけど…あれば使ってしまう人から見れば便利だよね。
財形住宅貯蓄
財形住宅貯蓄は、自宅の購入や建設、部分的なリフォームなどに使うお金を作るための貯蓄制度です。
財形住宅貯蓄
=用途・目的は住宅の購入やリフォームなどにともなう資金づくり
=55歳未満まで、1人1契約まで可能
=事業主を通じて、定期的に賃金から天引きされる形で貯蓄する制度
=550万円までは利子等に対する非課税措置がある
財形住宅貯蓄の払い出しをする時は、一定の条件があり、条件に当てはまらない場合は払い出しができないこともあります。
(1)床面積要件--従来の50㎡という要件に加え、住宅の新築又は建築後未使用の住宅で、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものであるときは床面積が40㎡以上という要件が定められました。
(2)経過年数要件--中古住宅の取得について、従来の耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内という要件を廃止し、昭和57年1月1日以降に建築されたものという要件が定められました。
財形住宅貯蓄は、一般財形貯蓄とは違い、利子が非課税になるという特徴があります。

低金利時代の今はピンとこないかもしれないけど、1970~90年くらいまでは定期預金の年利が約6%もついた時代!今の米国株インデックスぐらいには増えたってことだよね。
財形年金貯蓄
財形年金貯蓄は、60歳以降に使う老後資産などに使うお金を作るための貯蓄制度です。
国民年金と同じように、老後に少しずつ受け取ることができ、受け取り期間は5年から20年の間で設定することができます。
財形年金貯蓄
=用途・目的は老後資産などにともなう資金づくり
=55歳未満まで、1人1契約まで可能
=事業主を通じて、定期的に賃金から天引きされる形で貯蓄する制度
=貯蓄型は550万円まで、保険型は385万円まで利子等に対する非課税措置がある

財形貯蓄制度は、3つの口座を併用することもできるし、どれか1つだけやるでもOKだよ。
\自分で貯金できる人になる!と思ったら、この記事もおすすめです(*´▽`*)/
減っていく財形貯蓄制度の導入率
1970年代から必要に応じて、制度は拡大していきますが、年々財形貯蓄制度の導入率は減っています。
【創業年別 財形貯蓄制度の導入率】
1980年以前:47.3%
1999年以前:28.0%
2000年以降:14.2%

引用:企業における退職金等の状況や財形貯蓄の活用状況に関する実態調査|厚生労働省
1980年以前は、画期的な制度として重宝されていたであろう財形貯蓄制度。大きな会社ほど導入率が多く、従業員数が300人以上の会社では73.3%が導入していました。

当時は財形貯蓄制度のような福利厚生がしっかりしている会社はすばらしい!という流れもあったようです。大企業の普及率が高いのもわかる気がしますね。
しかし、状況は変わります。
現在もそのまま財形貯蓄制度を利用している方もいらっしゃいますが、「財形貯蓄制度はやめたほうがいい」とおっしゃるファイナンシャルプランナーなどの専門家も増え、現在では解約される方も多くなりました。
かつてはサラリーマンの資産形成を支えた制度である「財形貯蓄制度」。
なぜオワコンと言われるほど、解約する人が増え、導入する会社も減っているのでしょうか?

ここからは、財形貯蓄制度の具体的なメリットとデメリットを整理して見ていくよ。
財形貯蓄制度のメリット
財形貯蓄制度のメリットは、以下の6つです。
目的別の資産形成ができる
給与天引きで自動貯蓄ができる
低金利の公的住宅ローンを利用できる
制限なくいくつでも口座を持ち、併用できる
利子が非課税で受け取れる
財形給付金がもらえる
一つずつ見ていきましょう。
目的別の資産形成ができる
財形貯蓄制度がスゴイのは、目的ごとに自分の資産を管理して、増やすことができることです。

そんなの自分で口座を分ければいいじゃん!

そうなの。笑 でも、それができない人もいるからね。
自分で管理しなくても、勝手に会社がやってくれるのはありがたくない?
財形貯蓄制度は、人生の大きな出費である「住宅」と「年金」、そして、「それ以外(一般)」の3種類の目的ごとに、自分のお金を管理できるというメリットがあります。
貯蓄用の口座に入っているお金は、緊急の出費やちょっとした物欲によって、安易にムダづかいをしてしまいがち。
しかし、財形貯蓄なら「住宅」と「年金」に関するお金を、先に給与から天引きするため、意図しない出費を防ぐことができます。
さらに、「マイホームを買うためのお金」「老後の生活のためのお金」と用途を分けることで、貯金するモチベーションも保ちやすくなる効果があります。
最近はお金の使い方も多様化しているので、「住宅」と「年金」と「一般」の3種でいいのかという問題はあるものの、目的別の資産形成を勝手にしてくれるのは、ありがたいことです。

住宅は一生賃貸って方も増えてるよね。この分け方自体は、若干昭和っぽいので見直す必要があるかもしれません。
給与天引きで自動貯蓄ができる
財形貯蓄は、給与から天引きされ、自動で貯金ができるというメリットがあります。

自分で管理できない人でも、継続的に貯蓄することができます!…つくづく思うけど、財形貯蓄って国民の資産管理能力を信じてない制度だよね。笑
本来なら、自分で自分の資産を用途別に振り分けて、先に必要経費を必要なところに使う作業が必要です。
住宅・家賃のための貯金
老後のための貯金
住民税や国民年金のための必要経費
教育のための必要経費
生活のための必要経費 など
しかし、財形貯蓄制度は先に給与からの天引きされるので、貯蓄ができない人でも、無理なくまとまった目的別の資金を作ることができるでしょう。

正社員以外のアルバイト、パートタイマー、契約社員、派遣社員でも、条件によっては財形貯蓄制度を使うことができるので、気になる人は問い合わせしてみてね。
低金利の公的住宅ローンを利用できる
財形貯蓄制度に加入すると、低金利の公的住宅ローンを受けることができます。
財形貯蓄制度で受けられる住宅ローンの名称は、勤務先が提携している金融機関ごとに異なりますが、低金利の公的住宅ローンであることには変わりがありません。
住宅金融支援機構や共済組合の場合:財形住宅融資
勤労者退職金共済組合の場合:財形持家転貸融資

勤労者退職金共済組合の場合は、「財形持家転貸融資」って呼ばれているよ。
財形持家転貸融資(公的住宅ローン)
=財形貯蓄を行う社員がその残高に応じて受けることができる低金利融資制度
=勤務先が勤労者退職金共済機構から資金を借り入れ、社員に転貸するしくみ
=残高の10倍以内で、限度額は4,000万円まで、返済期間は最長35年
勤務先が間に入って申し込むため、社員が個人で申し込むよりも借り入れしやすく、金利や返済期間などの条件も比較的良いとされています。

2023年10月1日現在の財形持家転貸融資の最新利率は、年0.99%です。
財形持家転貸融資と同じ固定金利型の住宅ローン「フラット35」の2023年11月の金利と比べてみると、その違いがわかります。
財形持家転貸融資の金利
年0.99%
住宅ローン「フラット35」の金利
| 融資率 | 金利の範囲 | 最も多い金利 |
|---|---|---|
| 9割以下 | 年1.960%~年3.530% | 年1.960% |
| 9割超 | 年2.100%~年3.670% | 年2.100% |

財形持家転貸融資の金利は、かなりの低金利です。
勤務先ごとに使える条件や内容が違うので、詳細は勤務先に問い合わせてみてね。
制限なくいくつでも口座を持ち、併用できる
財形貯蓄制度のうち、一般財形貯蓄は制限なくいくつでも口座を持つことができます。
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、1人1契約までというルールがありますが、一般財形貯蓄と併用して持つことが可能です。
| 種類 | 口座数制限 |
|---|---|
| 一般財形貯蓄 | 制限なし |
| 財形住宅貯蓄 | 1人1契約まで |
| 財形年金貯蓄 | 1人1契約まで |
一般財形貯蓄の口座は複数持つことができるので、目的別に資産を管理することも可能です。
子どもの大学資金用
家族留学資金用
結婚資金用
介護資金用など

全部天引きだから、確実に資金が作れます…!
…とはいえ、全部天引きされたら生活が大変そうだけど。笑
自分で複数の口座を管理するのがめんどうな方にとっては、資産管理の手間が省ける制度です。
利子が非課税で受け取れる
財形貯蓄制度のうち、一般財形貯蓄以外の財形住宅融資と財形年金貯蓄では、一定の利子を非課税で受け取ることができます。
わたしたちが銀行などの預貯金から得る利子は、一律20.315%の税金を支払う必要があります。
しかし、財形貯蓄制度を使うと、元本550万円までの利子には税金がかかりません。
例えば…その違いは、以下のとおり。
【一般口座の場合】
利息額:1,000円
税金:200円
取得金額:800円
【財形住宅融資と財形年金貯蓄口座の場合】
利息額:1,000円
税金:0円
取得金額:1,000円

今は超低金利時代で、ぜんぜん利子がつかないからメリットが小さいけど…
1970~80年代は、定期預金の金利が6%もありました。

例えば、1970~80年代に財形貯蓄制度の上限額550万円を預けていれば、33万円の利子がつきました。
そのため、6.6万円の税金を非課税にすることができたのです。
【一般口座の場合】
元本:550万円
利子額:33万円
税金:6.6万円
取得金額:26.4万円
【財形住宅融資と財形年金貯蓄口座の場合】
元本:550万円
利子額:33万円
税金:0万円
取得金額:33万円

バブル世代前の方たちが貯金を愛しているのは、昔は年利6%もついたからなんだよね…
財形給付金がもらえる
財形貯蓄を始めると、勤務先から財形給付金が支給されることがあります。
財形給付金制度・財形基金制度
=財形貯蓄を利用する従業員に対し、会社が行う貯蓄奨励策
=会社が毎年一定額の拠出を行い、7年経過ごとに拠出金と運用益の合計を従業員に支給
=会社の拠出金は、損金または必要経費として扱うことができる


給付金は毎年、勤労者1人につき最高10万円まで!
10万円はすごいなぁ…
財形貯蓄制度のデメリット
財形貯蓄制度は多くのメリットがありますが、近年は導入する企業が減っています。
1980年代には、約半数の企業が導入している人気の制度でしたが、2000年以降は導入企業が15%に留まる結果に。

引用:財形貯蓄制度導入率|独立行政法人労働政策研究・研修機構
その理由は、そもそも従業員に導入してほしいというニーズがなくなってしまったことが大きいようです。

引用:財形貯蓄制度導入率|独立行政法人労働政策研究・研修機構

低金利時代に突入したこと、新しいNISAやiDeCoなどのもっと自由度が高く、デメリットが少ない制度が生まれたことも関係がありそう…。
財形貯蓄制度は、「オワコンだ」「意味ない」と言われてしまう理由となる、デメリットも整理してみましょう。
利子が低すぎて意味がない
引き出すのが大変で自由度が低い
目的外の払い出しは課税の対象になる
別の財形所畜への預け替えはできない
退職・転職すると継続できない
iDeCoのような所得税控除がない
インフレリスクに弱い
一つずつ見ていきましょう。
利子が低すぎて意味がない
財形貯蓄制度を利用するデメリットとして大きいのは、利子が低すぎて意味がないことです。

この理由がいちばん大きいかも…。
前述したように、財形貯蓄制度は定期預金に預けておくだけで金利が6%もついた1980年代に人気があった制度です。
2000年代以降の金利は、0.01%程度まで落ちているため、利子分の税金が非課税になったところで、大した意味がありません。

利子の非課税措置の恩恵を受けられなくなってしまいました…。今は、自分で投資をしたほうがお金が増える時代だよね。
さらに、増えないお金が給料天引きでとられてしまうとなると、他の資産に変えてお金を増やすことができず、機会損失になってしまうというデメリットに繋がります。

機会損失は大きなデメリットです。
昔は定期預金で増やせたけど、今同じリターンを得たいなら、リスクをとって投資信託や株式に変える必要があります。
増やせない大金を財形貯蓄制度で積み立ててしまうのは、もったいないと考える人がいてもおかしくないでしょう。
同じように利益分が非課税になる制度なら、新NISAやiDeCo(イデコ)などの時代に即した制度も生まれています。
引き出すのが大変で自由度が低い
財形貯蓄制度は、給与から天引きされ、目的ごとに資産を管理する制度です。
かんたんに引き出せてしまうと、目的が達成できないため、そもそも引き出しにくい仕組みになっています。
お金を引き出したい時は、所定の手続きが必要で、とても手間がかかります。

銀行預金みたいに、キャッシュカードでかんたんにお金が下せるわけではありません。
財形住宅貯蓄の払出方法には、「残高の一部払出し」「残高の全額払出し」「口座解約」の方法がありますが、払出事由により制約があります。また、払出時には取得したこと、居住していることを証する書類の提出が定められています。提出書類は原本または写しのいずれでも可能です。

うわぁ…書類が必要なのかぁ。めんどくさいなぁ…。笑
目的外の払い出しは課税の対象になる
財形貯蓄制度のうち、住宅と年金が目的の「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」は、目的外の用途で払い出すと、利子が非課税にならないというペナルティがあります。

なんそれ、意味ないじゃん!ww
そもそも財形貯蓄制度は、自分の給料が原資であるにも関わらず、目的外の引き出しにペナルティがあることに違和感を持つ方も多いのだとか。
利子の非課税が大きなメリットであるにも関わらず、解約時には20.315%の税金がかかります。
また、課税対象になるのは、その時の利子だけではありません。
過去5年間で得られた利子すべてが課税対象となるので注意が必要です。
別の財形所畜への預け替えはできない
財形貯蓄制度には、「財形住宅貯蓄」、「財形年金貯蓄」、「財形一般貯蓄」の3種類がありますが、別の用途で作った財形貯蓄口座への預け替えは一切できないことになっています。

マイホームはあきらめて、「財形住宅貯蓄」から「財形年金貯蓄」に変更しよう!
…とは、いかないわけです。うむ。
預け替えはできませんが、併用は可能なので、もし「財形年金貯蓄」をはじめたければ、「財形住宅貯蓄」はそのままに別途積立を開始することができます。
でも、給与からの天引き額が増えてしまうため、実際はダブルで使用するのが難しく諦めるケースも多いのだとか。
また、「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」は、別の金融機関の財形商品への預け替えもできませんので注意が必要です。

一般財形貯蓄の場合のみ、3年以上積立を続けていれば、預け替えができるよ。
退職・転職すると継続できない
財形貯蓄制度は、転職先も財形貯蓄制度を利用している場合は、退職から2年以内に手続きを行えば、引き継ぎすることができます。

逆に言うと、転職先が財形貯蓄制度を利用していない場合は、引き出しや解約が必要です。
2年以内であれば、金融機関に資産を補完しておくことができるので、2年後の状況を見て積立を続けられない(制度がない企業に勤務している状態)場合は、資産の払い出しが必要になります。

転職や退職は、目的外(住宅や年金)の解約になるので、利子に対して5年間さかのぼって課税される点に注意が必要です。
財形貯蓄制度の導入率が減っている原因のひとつが、この乗り換えが難しい点です。
今は財形貯蓄制度の導入数自体が減っていますから、退職・転職すると財形貯蓄制度がない企業に就職するケースも多くなっています。

財形貯蓄制度がある企業だけしか、転職希望をださない…とかはあり得ないと思うので、結果的にどんどん利用者が減ってしまうよね…。
iDeCoのような所得税控除がない
財形貯蓄制度が昭和の資産形成サポート&税制優遇制度だとしたら、iDeCo(イデコ)は令和の資産形成サポート&税制優遇制度だと言えそうです。
しかし、財形貯蓄制度は、利息分に対して非課税になるだけで、とても限定的な印象があります。
一方、iDeCo(イデコ)は、拠出金が所得税の控除となるため、財形貯蓄制度よりもさらに税制優遇が強化された仕組みが採用されています。
iDeCo(イデコ)と財形貯蓄制度の違いは、以下の通り。
| 財形貯蓄制度 | iDeCo(イデコ) | |
|---|---|---|
| 加入資格 | 会社員のみ | 会社員、自営業者、主婦など |
| 投資額の上限 | 預貯金: 元利合計550万円まで非課税(財形住宅貯金と合算して) 保険:385万円 (超過分の運用益は課税) | 職業によって異なる (144,000円/年 ~816,000円/年) |
| 税制優遇 | 拠出時 所得控除なし 運用時 運用益は非課税 払出時 非課税 | 拠出時 全額所得控除あり 運用時 運用益は非課税 払出時 課税 (ただし、年金受取は公的年金控除を、一時金受取は退職所得控除を適用可) |
財形貯蓄制度は、給料から天引きして用途別の口座に振り分けられるだけなので、厳密にいえば掛金ではなく、所得控除の対象にはなりません。
現役時代に支払う所得税もなるべく減らしたい場合は、iDeCo(イデコ)で運用する必要があります。

拠出時の所得控除は、最近できた一般NISA、つみたてNISA、新NISAにもないiDeCo(イデコ)独自のメリットだよ。
\iDeCo(イデコ)が気になったら、この記事もおすすめです(*´▽`*)/
【合わせて読みたい】
iDeCoはやめとけ!理解しないで始めるとやばい?その理由とデメリット3選
インフレリスクに弱い
財形貯蓄制度は、インフレ時には資産価値が目減りしてしまうリスクが大きい制度です。
インフレーション
=商品の値段(物価)が上昇傾向になること
なぜなら、そもそも財形貯蓄の利子はとても低いから。
金融機関によって金利にばらつきはありますが、もうほぼゼロと言っても過言ではないのが現状です。

そんな中、日本銀行は物価上昇率の目標を2%に定め、デフレ脱却を目指しています。
日本銀行は、2013年1月に、「物価安定の目標」を消費者物価の前年比上昇率2%と定め、これをできるだけ早期に実現するという約束をしています。
インフレが進む中、利子はほとんど変わらないので、財形貯蓄制度はますます意味のないものになっていきます。
10年前に財形貯蓄口座に入っていた10,000円は、今、財形貯蓄口座に入っている10,000円とは価値が違います。
財形貯蓄制度が始まった、昭和47年と平成24年の大卒初任給を比較してみると、なんと4倍。
| 年 | 大卒初任給 |
|---|---|
| 1972 (昭47) | 52,700円 |
| 1982 (昭57) | 127,200円 |
| 1992 (平4) | 186,900円 |
| 2002 (平14) | 198,500円 |
| 2012 (平24) | 201,800円 |
財形貯蓄制度の口座の中のお金は、多少の利子を受け取ったところで、インフレの上昇には追い付かず…かなり目減りしてしまうことが予想できます。

財形貯蓄制度を使ってお金を増やすという発想は、もう古いものだということがわかります。
財形貯蓄がおすすめの人
財形貯蓄制度を使ってお金を増やすのは難しいものの、税制優遇や有利な住宅ローンの使用など、個々の事情によっては、メリットに感じる方ももちろんいると思います。
財形貯蓄がおすすめの人は、こんな人です。
貯蓄を自動化したい人
マイホームの購入を検討している人
一つずつ見ていきましょう。
貯蓄を自動化したい人
貯蓄がとにかくニガテで、一切お金のことを考えたくない人は、財形貯蓄制度を利用するのもひとつの手です。
財形貯蓄は、給与から自動で天引きされるため、一切お金のことを考えなくても、決まったお金がプールされていきます。

本当になにもする必要がありません。笑
自分で貯蓄することができない、手に入れたお金は全額ムダづかいをしてしまう、お金のことを一切考えたくない人にとっては、とても便利な制度だと言えます。
マイホームの購入を検討している人
将来的にマイホームの購入を検討している人なら、財形貯蓄制度を使うメリットを感じられるかもしれません。
住宅購入用の資金を自動で天引きするため、確実に大きなお金を貯めることができますし、勤め先によっては低金利の住宅ローンを組める可能性があります。
個人で借りようとすると審査が下りなかったり、条件が悪いこともあるかもしれませんが、その点は期待できるかもしれません。
財形貯蓄がおすすめできない人
一方、財形貯蓄がおすすめできない人は、こんな人です。
資産を増やしたい人
自分で勉強して投資をする意欲がある人
一つずつ見ていきましょう。
資産を増やしたい人
財形貯蓄制度を使って、資産を増やすのは難しい時代が来ています。
銀行預金よりは利子が高い傾向にあるとはいえ、今後財形貯蓄制度の金利が大きく上がることは期待できません。
さらに政府は、2%のインフレ目標を掲げていますので、これからさらに財形貯蓄口座のお金は、目減りしていくことが予想できます。
サラリーマン(従業員)と直接接点のある企業が、給与から天引きという形で強制的に貯蓄させます。そのため、貯蓄がニガテな人でも継続的に貯蓄ができます。

銀行に預けているだけで、年利6%も増えた時代とは違うのだよ…。泣
自分で勉強して投資をする意欲がある人
「お金の勉強をしたい」、「自分の資産は自分で育てたい」という意欲がある方は、財形貯蓄制度を使って資産運用をするのは、あまりおすすめしません。
なぜなら、もっと時代に即した制度がどんどん生まれ、また自分で自分の資産を管理しやすいサービスがたくさん生まれているからです。
2024年からはこれまでの「つみたてNISA」と「NISA」が「新NISA」として生まれ変わりますし、令和の財形貯蓄制度ともいえる、iDeCo(イデコ)を利用するという選択肢もあります。
さらに、自分でネット証券口座を作って、株や投資信託を追加で買い付けることで、さらなるリスク分散をするという方法も。

もちろんお金のことを考えたくない人は、ストレスになってしまうのでおすすめしません。
でも、ちゃんと管理したい人はいくらでも自分で情報収集ができる時代です。
財形貯蓄制度よりおすすめの資産運用
財形貯蓄制度よりおすすめの資産運用法のうち、国がおすすめしている2つの制度をご紹介します。
新NISA
iDeCo(イデコ)
一つずつ見ていきましょう。
新NISA
2024年から現行の「つみたてNISA」と「NISA」が、「新NISA」として生まれ変わります。

せっかくの生まれ変わりのタイミングなので、ぜひはじめちゃいましょう!笑
財形貯蓄制度は、給与からの天引きによるものでしたが、「新NISA」でも証券会社の積立設定などを利用すれば、同じように資産運用を自動化することが可能です。
金融機関によっては、最低100円からでも資産運用が始められますし、いつでも現金化することができるので、財形貯蓄制度よりもかなり自由度が高くなっています。
さらに、選べる投資先も多く、各証券会社がお金の勉強をしたい人向けにいろんな情報を提供し、セミナー等も開催してくれているため、口座を開くだけでも投資の勉強になります。

投資初心者向けのコンテンツもめちゃくちゃ多いので、まずは証券会社の口座開設をしてみることがおすすめです。
新NISAは、大きく分けると「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つがあります。
それぞれの年間投資枠は、120万円と240万円で、合計360万円まで、非課税で投資することが可能です。

旧NISAと比較すると、投資できる金額がめちゃくちゃ増えました!
欲を言えば、もっと若い時からやりたかったなぁ…!
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |
| 非課税保有限度額 | 成長投資枠と合わせて 1800万円まで | 成長投資枠のみなら 1200万円まで |
| 口座開設期間 | 恒久化 | 恒久化 |
もちろん投資には必ずリスクが伴いますので、自分のリスク許容度を把握しながら、ゆっくり投資に慣れていくことが大事です。

長期のコツコツ投資がいちばんです!
\NISAが気になったら、この記事もおすすめです(*´▽`*)/
【合わせて読みたい】
財形貯蓄制度と積立NISAは併用する?どっちかやめる?2つの制度を徹底比較
iDeCo(イデコ)
財形貯蓄制度のうち、財形年金貯蓄の生まれ変わりと言っても過言ではないのが、このiDeCo(イデコ)です。
iDeCo(イデコ)
=個人型確定拠出年金制度
=目的は老後の資産作り
=一定額を毎月積み立てて、積み立てた資産や運用益を60歳以降に受け取ることができる
前述したように、iDeCo(イデコ)と財形貯蓄制度の違いは、以下の通りです。
| 財形貯蓄制度 | iDeCo(イデコ) | |
|---|---|---|
| 加入資格 | 会社員のみ | 会社員、自営業者、主婦など |
| 投資額の上限 | 預貯金: 元利合計550万円まで非課税(財形住宅貯金と合算して) 保険:385万円 (超過分の運用益は課税) | 職業によって異なる (144,000円/年 ~816,000円/年) |
| 税制優遇 | 拠出時 所得控除なし 運用時 運用益は非課税 払出時 非課税 | 拠出時 全額所得控除あり 運用時 運用益は非課税 払出時 課税 (ただし、年金受取は公的年金控除を、一時金受取は退職所得控除を適用可) |

所得控除があるのはとてもありがたいですね。
iDeCo(イデコ)は、とても有利な制度ではありますが、新NISAに比べると注意点が多いと言われています。
・専用口座の開設に手数料が発生することがある
・60歳までは元金&利益ともに取り崩すことができない
・資金を受け取るときに課税される場合がある など
iDeCo(イデコ)を脱退して一時金を受け取ることができるケースもありますが、それはかなりまれな状況です。

基本的には60歳までは引き出せないので、「急にまとまったお金が必要になったから取り崩したい」と思っても難しいと思ったほうがよいでしょう。
また、iDeCo(イデコ)を年金として分割で受け取る場合、65歳以上で公的年金等の収入が110万円以下であれば課税されません。
しかし、110万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

財形貯蓄制度は払い出し時は非課税だったので、iDeCo(イデコ)には注意が必要です。
\財形貯蓄制度の罠に気がつける自分になる!と思ったらお金の勉強をはじめよう(*´▽`*)/
まとめ:財形貯蓄やめたほうがいい?意味ない理由と7つのデメリット
財形貯蓄は、昭和から愛されてきた会社員の資産づくりをサポートする制度です。
金利が高かった時代には、利用者数も右肩上がりだったのですが、今ではメリットが限定的で、誰もが利用しやすい制度ではなくなっています。
【財形貯蓄のメリット】
目的別の資産形成ができる
給与天引きで自動貯蓄ができる
低金利の公的住宅ローンを利用できる
制限なくいくつでも口座を持ち、併用できる
利子が非課税で受け取れる
財形給付金がもらえる
【財形貯蓄のデメリット】
利子が低すぎて意味がない
引き出すのが大変で自由度が低い
目的外の払い出しは課税の対象になる
別の財形所畜への預け替えはできない
退職・転職すると継続できない
iDeCoのような所得税控除がない
インフレリスクに弱い
利用者が減っている大きな原因は、時代の変化です。
超低金利でインフレが進み、多様性が重要視される現代には、適さない部分(デメリット)も多いと言えるでしょう。
しかし、その一方で、強制的に給与から天引きして資産を作るしくみや低金利の公的住宅ローンが利用できることは、一部の方にとっては大きなメリットで、「貯蓄を自動化したい人」や「マイホームの購入を検討している人」にとっては、今でも有用な制度かもしれません。

わたしは自分で資産管理をしたいので、財形貯蓄制度へのニーズはないけど、すごくありがたい制度なのかも!
気になる方は、ぜひ勤め先の担当部署に問い合わせてみてください。
自分には合わないかなぁ…と思ったら、ぜひ、自分で資産を管理する方法を検討しましょう。
それでは今日も、まめまめたのしい一日を。
\枝豆の資産管理方法が気になる人は、こちらの記事もおすすめです(*´▽`*)/
【合わせて読みたい】
失敗しない貯金の仕方!5000万円貯めたわたしの口座の分け方と具体的な3つの手順