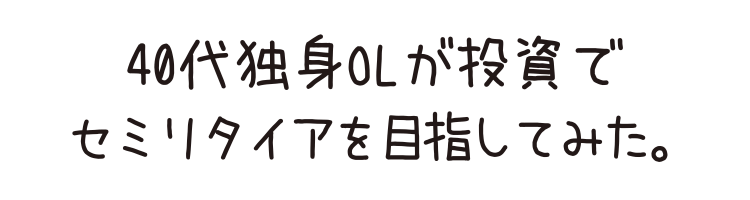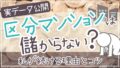40代の場合、アセットアロケーション&ポートフォリオは
どんな組み方をしたらいいの?
2024年に始まった新NISAの影響で、資産運用を始める人が増えています。
特に私も含めた40代は、今立てた戦略が老後の生活に大きく影響することがわかってくる年。
のんびりしている余裕もないし、かといって手遅れでもないので、とにかく参考になるデータがたくさんほしい!と思う人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、恥ずかしながら40代独身OL投資家であるわたしのアセットアロケーション&ポートフォリオを大公開!
若干、一般的ではないのはわかっていますが、私なりのこだわりポイントとともに、40代のアセットアロケーション&ポートフォリオの組み方を整理してみたいと思います。
▼本記事の内容
40代のアセットアロケーション&ポートフォリオの参考例
40代のアセットアロケーション&ポートフォリオの組み方
ご紹介内容はあくまで個人の見解と運用実績であり、正確性や安全性を保障するものではありません。また情報提供のみを目的としており、投資、法務、税務その他のアドバイスを意図しているわけでもありません。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。詳細はこちら
大公開!40代独身OLのアセットアロケーション&ポートフォリオ
まず、アセットアロケーションの前に「無リスク資産」と「リスク資産」の割合から。
一般的に無リスク資産とは、収益が確定している資産のことを指します。
無リスク資産=収益が確定している資産のこと。別名:安全資産
リスク資産=収益が確定していない資産のこと。別名:危険資産
厳密な分け方は難しいですが、一般的に無リスク資産とは、先進国の短期国債や現金、預貯金、定期預金などのことを指します。
一般的に元本割れしにくい資産です。

もちろんインフレリスクなどは普通にあるので、無リスク資産でも価値が下がらないというわけじゃないですよ。下がるときは、下がる!笑
40代独身OLの枝豆の場合は、こんな感じ。
リスク資産:93%
無リスク資産:7%

うーん、リスキーです。笑
ただ、完全に無リスクな資産なんてないですからね。(いいわけ)
私の場合はほとんどリスク資産ですが、これはあえてそうしています。
リスクとリターンは背中合わせであり、リターンを得たければ、リスクをとっていく必要があります。
今は資産構築目標(1億6000万円)に向かって適切なリスクをとっていくべき時期だと思っているので、資産のほとんどをリスクにさらしていくことを目指しています。

このリスク資産の割合を踏まえたうえで、アセットアロケーションを見ていきます。
\私の詳細な資産運用目標はこちらから確認できます(*´▽`*)/
【合わせて読みたい】わたしの投資運用方針と資産目標
アセットアロケーション
アセットアロケーションとは、一般的に「資産配分」のことを指します。
ざっくり分けると、こんな感じ。
国内株式
外国株式
国内債券
外国債券
不動産
コモディティ(金、原油など)
現金
実は、意外や意外、資産運用を始めたばかりのころは、めちゃくちゃ真面目にアセットアロケーションを考えて資産運用をしていました。

根が真面目なもので…笑
でも、いろんな相場を経験し…リスク許容度も大きくなり、資産運用しているうちに大きな目標もできてきて、今は見るも無残な素人っぽい配分になりつつあります。

普通は勉強すればするほど、分散投資の重要性に気が付くものなのですが…
リスク許容度が大きくなるのも考え物です 笑
【40代独身OLの枝豆のアセットアロケーション】
| 国内株式 | 2% |
| 外国株式 | 51% |
| 国内債券 | 0% |
| 外国債券 | 2% |
| 不動産 | 40% |
| コモディティ(金、原油など) | 0% |
| 現金 | 5% |

円グラフにすると、こんな感じです!

リスク資産の5割が外国株式で、4割が現物不動産。
そして、のこりの1割に日本株式、外国債券、現金が振り分けられています。
コモディティは0%になっていますが、少なすぎて%に換算されないだけで、厳密に言えば0%ではありません。1%以下ですが、暗号通貨のビットコインが入っています。
国内債券は、まったくもっていません。
資産運用を始めた当初は、国債を買っていましたが、償還とともに0%に。その後は、再購入していません。
国債は元本割れがなく、安心できる資産のひとつ。
資産を守る時期になったら、また個人向け国債の変動金利10年の購入を検討するかもしれません。
でも、現状は目標達成に向けてもうちょっとリスクをとっていきたい気持ちが強く、直近で買う予定はありません。

引用:個人向け国債|財務省
また、ぱっとみで目立つのは、現物不動産の割合の高さです。

不動産、40%もあるんだなぁ…!
個人が現物不動産を持ってしまうと、どうしても不動産の割合が多くなります。
これは不動産投資をしている以上、しょうがないこと。
私が持っているのは国内不動産なので、国内不動産のREITは購入しないようにしています。
海外REITは気にならないわけではないけど、やっぱり今は不動産にはそこまで大きな興味はなく、アセットアロケーションのバランスを変更していくとしたら、コモディティの暗号資産をもっと増やしていきたい気持ちのほうが強いです。

ビットコインは定期積立をしていますが、どこかのタイミングでスポット買いをしたい!と思いながら、時間が経ってしまっています。タイミングが難しい…笑
見る人が見たら怒られそうなアンバランスかつ乱暴なアセットアロケーションではありますが、私個人の現状の気分としては、外国株式5割、不動産4割、その他1割という全体的な割合自体は、理想通り。
今後は資産全体を増やしながら、その他のコモディティ(主にビットコイン)の割合を増やしたいと考えています。
ポートフォリオ
ポートフォリオは、アセットアロケーションとは違い、具体的な資産のうちどの商品を持っているかを表す言葉です。


どんな銘柄を買うかとか、どの物件を買うか…みたいな少し細かい話になります。
40代独身OLの私の現物不動産を除いたポートフォリオは、以下のとおり。
【40代独身OLの枝豆のポートフォリオ】
| 投資信託 S&P500系 | 60% |
| 投資信託 NASDAC系 | 30% |
| 米国株(個別銘柄) | 4% |
| ETF 米国テック系 | 2% |
| その他 | 4% |
私はオールカントリーよりもS&P500が好きなので、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)や楽天オルカンなどの全世界系の投資信託は持っていません。
純資産総額の割合が多いのは、以下の3つの投資信託です。
emaxis slim 米国株式(s&p500)
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
同じS&P500系の金融商品である、「emaxis slim 米国株式(s&p500)」と「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」を両方持っているのは、大きな意味はなく…長く運用していると、どうしても後から信託報酬の安い金融商品が出てきてしまうため、気まぐれで両方買っているだけ。

どうしても購入時期によって、総コストが大きい方は変わってくるんですよね…。
いろいろ買ってみた結果、どちらも低コストでリターンも優秀、純資産も伸びていて、さらに同じインデックス(指標)なので、もうそんなに気にしなくてもいいかなと思ってはいます。
海外ETFのほうがコスト面が有利なのはわかっているのですが、基本的にはほったらかし投資推奨派のため、自動で再投資してくれる投資信託のほうが好みです。
「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」がベンチマークとするNASDAQ100インデックスは、米国ナスダック市場に上場する企業のうち時価総額上位100社の株式で構成される株価指数です。
現状テック系企業が多く含まれますが、定期的に勝手にリバランスされることもあって、長期ほったらかしでも順調に伸びてくれるのではないかと期待しています。
\S&P500が気になる方は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/
新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠
投資信託は、新NISAのつみたて投資枠と特定口座の両方で積立しています。
新NISAのつみたて投資枠は、もう老後まで長期運用でほったらかし予定なので、あまり細かく銘柄変更をするつもりはありません。

現状は、比較的安定運用でいけそうな米国株投資信託の「emaxis slim 米国株式(s&p500)」で全枠埋めようとしています。
一方、特定口座では、同じように「emaxis slim 米国株式(s&p500)」を毎月10万円分を買いつつも、「iFree NEXTインド株インデックス」を毎月3万円分積み立てています。
iFree NEXTインド株インデックスを新NISAのつみたて投資枠で買わないのは、まだインド株が信用できていないからです。笑

昔、ブラジル株を長期で積立続けた結果、ぜんぜん育たなかった(むしろちょっとマイナス)…という経験をしているので、そうなる可能性もゼロではないような…気がしているんですよね。
新NISA枠のつみたて投資枠は、2023年までのつみたてNISAとは違って恒久的に枠が利用でき、半永久的に利益が非課税になりました。
その一方で、損失が出てしまった場合、損益通算や繰越控除ができないという仕組みになっています。
Q:NISA口座で保有する金融商品(株式・投資信託等)を売却した際に損失が生じた場合、他の証券口座(一般口座・特定口座)で生じた利益と損益通算することはできますか?
A:NISA口座では、株式や投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
引用:NISA Q&A|金融庁
インド株はインフラ面は整っていき、人口も増えていくのが確定ではありながら、政治面で不確定要素が多いというデメリットがあり、正直まだどうなるかわかりません。
そうなると、やっぱり安心なのは米国株。
つみたて投資枠は、期待以上にならない可能性はあるにせよ、長期で安定的に育ってくれそうな米国株で埋めたい気持ちがあり、NISA口座ではインド株を購入するのを辞めました。
私はNISA口座への参入が遅く、始めたのは2021年です。
2014年1月にNISA制度ができた当初、証券会社に直接話を聞きに行っているのですが、そのころはあまりにも枠が小さくてあんまり興味がありませんでした。

年間40万円って意味ないじゃん…みんな興味なさそうだし、あんまり続かなそう…って思って、スルーしてたんですよね…笑
ちょっとしくじりました。笑
過ぎた分はしょうがないけど、新NISA開始の2024年からはNISA口座優先で、最速で枠を埋めていきたいと思っています。
そのため、成長投資枠はちょっとだけリスクをとって、米国株のNASDAQ100に投資していきます。
「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」と「<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックス」で迷ったのですが、手数料が低く抑えられた「<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックス」を買いはじめました。
\ナスダックが気になる方は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/
【合わせて読みたい】NASDAQ100はやめとけと言われる理由!リスク管理のための完全ガイド
40代独身OLのアセットアロケーションのこだわりポイント
40代独身OLであるわたしのこだわりポイントを整理してみると、以下のとおり。
特定口座は目標達成スピード重視!リスク高めで設定
NISA口座はほったらかし重視!個別株やETFは入れない
不動産(現物)を所持しているのでリートは入れない
一つずつ見ていきましょう。
特定口座は目標達成スピード重視!リスク高めで設定
私のアセットアロケーションの一番の特徴は、債券がほぼ含まれていないことです。

以前は債券を買っていたのですが、目標設定を明確にしてから、買わなくてもいいかなと思うようになりました。
今は資産を増やしていきたい運用時期なのと、資産運用に慣れて自分のリスク許容度がわかってきたこともあり、今はリスクがあるのは承知の上で、債券比率をかなり減らしています。

良い子はマネしないでね。笑
債券の組み入れ割合については、最近いろんなメディアで議論されているのを見かけるようになりました。
昔と比べて「債券って本当に必要?」と思う方が多くなってきているのだと思います。
というのも私たちの年金の運用を行っている、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)でさえ、近年債券の割合を減らしているんです。
GPIFは2010年ごろまでは、国内債券を約70%も組み入れた保守的な運用をしていましたが、最近は国内債券の目標割合を25%まで落としています。
国内債券:25%
外国債券:25%
国内株式:25%
外国株式:25%
個人の資産と比べて、保守的な対応が必要とされるGPIFでさえ少し考え方を変えてきているのは注目です。

アセットアロケーションを考える時は、自分の資産運用の目標とリスク許容度、そして市場環境など幅広く加味して決めていくのがおすすめです。
\米国債が気になる方は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/
NISA口座はほったらかし重視!個別株やETFは入れない
私の資産運用のもう一つの特徴は、NISA口座を完全にほったらかし重視の投資枠にしようとしていることです。
NISA口座は運用益が非課税になるため、運用益が出やすい銘柄を組み入れていくのが良い一方で、売却のタイミングが悪いと枠の復活までに時間がかかるリスクがあります。
上手くタイミングを計ればもっと賢い運用ができるかもしれませんが、わたしはその時間を投資に使う必要性をあまり感じないため、何か大きな問題が起こらない限りは1度も売却しないまま、老後資金として枠を最大限有効活用する戦略をとることにしました。(今のところ)
そのため個別株は組み入れず、さらに分配金の再投資が必要なETFも組み入れず、投資信託一本でいこうと思います。
それもインド株や中国株などのちょっと情勢が読みにくい投資信託は除外し、現状は右肩上がりで伸びてくれそうな米国株投資信託を組み入れる戦略でいきたいと思います。
不動産(現物)を所持しているのでリートは入れない
個人のアセットアロケーションとして、不動産(現物)が含まれているのはめずらしいかもしれません。
不動産(現物)などのオルタナティブ資産を組み合わせると、ポートフォリオが安定してくれる一方で、個人のポートフォリオとしては偏りが生じやすくなります。

ちょっと…不動産資産が多すぎるかなという気もしなくはないのだけど…
ただ現金が少ない分、不動産が疑似安定資産のような形でどしっと構えてくれているのは、精神的にもとても助かっています。
もし不動産(現物)を買っていない場合は、小口で投資ができる不動産ファンド「J-REIT」や株式投資型クラウドファンディング、なども検討したいのですが、現状は現物割合だけでも大きくなってしまっているため、今すぐ購入したい希望はありません。
ただ、やっぱり不動産があるとアセットアロケーションが安定するように感じるのと、会社員のメリットを生かしたレバレッジが効かせられるため、良い物件があれば現物資産の買い足しや新しい不動産関連商品に挑戦したい気持ちもあります。

アセットアロケーションに、万人の正解はありません。資産運用の目的や思い描く未来像、リスク許容度によって正解は変わるので、自分が納得できる割合を探してみてください。
\REIT(リート)が気になる方は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/
【合わせて読みたい】REIT(リート)はやめとけ!不動産投資信託をおすすめしない7つの理由
40代の資産運用!アセットアロケーションの組み方

ここまで紹介しておいてなんだけど、投資歴15年&40代の枝豆のアセットアロケーションは、いわゆるお手本にしやすいアセットアロケーションではありません。笑
ここからは、今40代のみなさんがアセットアロケーションを組む際の組み方の基本と注意点をまとめてみましょう。
なぜアセットアロケーションが大切なのか?
債券の割合=年齢は本当にベストなの?
年金積立金に学べ!基本ポートフォリオ(GPIF)
米国の年金積立金に学べ!応用ポートフォリオ(CaiPERS)
定年以降も働くなら、投資商品が多めでも悪くない
年金の繰り下げ受給ができるぐらいの資産構築が理想
アセットアロケーションは定期的に見直す
一つずつ見てみましょう。
なぜアセットアロケーションが大切なのか?
資産運用を始める時、どの銘柄を買おうか迷うところから始める人が多いと思います。
でも、ちょっと順番が違います。
資産運用を始める時は、最初にアセットアロケーションを定め、その後にポートフォリオ(銘柄選び)を定めるのがおすすめです。
最初に自分のリスク許容度に合わせた資産バランスを組み立てたのちに、中身の金融商品を選びましょう。
また、リスクを抑えるには、相関性の低い資産クラスを組み合わせるのが有効です。
一般的に株式と債券は相関関係が低く、組み合わせることによってリスクを抑えることができます。
以下は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が公開している各資産の相関係数の表ですが、マイナス1に近いほど逆の値動きをする傾向が強いことを表しています。

引用:相関係数とは|年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)
引用:資産クラス間の相関|J.P.モルガン・アセット・マネジメント

外国株式を買いすぎたかも…と思ったら、国内債券で中和する…みたいにバランスをとっていきます。
債券の割合=年齢は本当にベストなの?

40代の場合、適切な債券割合ってどのくらいがベストなの?

資産運用の基本として、「債券の割合=年齢」が良いってよく言われているよ。
一般的に、株式と債券の比率は、年齢=債券の割合が良いとされています。
債券の割合=年齢
株式の割合=100-年齢

例えば、40歳なら債券40%、株式60%。45歳なら債券45%、株式55%ってことです。
ただし、この式は少しずつ現代人には合わなくなってきていると言われています。
なぜなら、私たちの生き方が多様化しているから。
現代の40代は既婚か未婚か、子どもがいるかいないか、資産運用経験や経済状況によって最適な比率が変わる可能性が高いのです。
年金積立金に学べ!基本ポートフォリオ(GPIF)

40代って、リスクをとりすぎることもできないけど、とれないこともないっていうなかなか難しい年齢だよね。
そんな時参考になりそうなのは、今実際に年金積立金を管理運用している年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオの考え方。
彼らの今現在のポートフォリオは、それぞれの資産構成を均等に25%で割っています。
| 国内債券 | 外国債券 | 国内株式 | 外国株式 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産構成割合 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 乖離許容幅 | ±7% | ±6% | ±8% | ±7% |
引用:将来の公的年金の財政見通し(財政検証)|厚生労働省

初心者投資家の場合は、とりあえずGPIFの割合を真似してみるのもありかもしれません。
米国の年金積立金に学べ!応用ポートフォリオ(CaiPERS)
では、もう少し積極的に運用したい人のために、米国のケースも参考にしてみましょう。
運用資産が40兆円規模の巨大運用団体である、カリフォルニア州職員退職年金基金「カルパース(CaiPERS)」。

カルパース(CaiPERS)は年金基金の中では、比較的積極的な運用をする基金として世界でも有名です。
カルパースの目標ポートフォリオは、以下のとおり。
【直近のカルパースの目標ポートフォリオ】
| 2014年3月 | 2017年12月 | 2021年11月 | |
|---|---|---|---|
| 世界株式 | 51% | 50% | 42% |
| 世界債券 | 20% | 28% | 30% |
| 不動産等実物資産 | 10% | 13% | 15% |
| 未公開企業投資 | 10% | 8% | 13% |
| 私募債 | – | – | 5% |
| 米国短期国債等 | 1% | 1% | – |
| インフレ連動債券等 | 6% | – | – |
| インフラ | 1% | – | – |
| 森林 | 1% | – | – |
| 合計 | 100% | 100% | 105% |
【2021年11月のアセットアロケーションの変更概要】
・負債比率は、運用資産額の5%に設定する (5%のレバレッジをかける)
・世界株式は、上場株市場がやや過熱気味に見えるため、50%から42%に引下げる
・世界債券は、28%から30%に引上げる
・不動産等実物資産は、13%から15%に引上げる
・未公開企業投資は、8%から15%に引上げる
・私募債は、新規で5%投資する
引用:CalPERS Selects Asset Allocation for Investment Portfolio
引用:Finance and Administration Committee
日本のGPIFが株式と債券の割合を50%:50%にしているのに対し、米国のカルパースは株式の割合がやや多め。

年金運用ってすごく保守的なのかと思ったけど、そうでもないですね。不動産などの実物資産やプライベートエクイティに20%も入れてるのはすごい。
プライベートエクイティ
=未上場企業に投資し、売却やIPO(新規公開)によって利益を得ること

IPO投資は、私も一時期ハマってしまったのだけど、利益が出る時は本当に大きく上がります。その分もちろん、下がる時は大きく下がるよ…。
定年以降も働くなら、投資商品が多めでも悪くない

ここまでの内容を参考にすると、40代の株式債券比率は、
だいたい株式50~60%、債券40%~50%が良いのかな…。

そうねぇ…。私みたいにほぼ90%株式はさすがに危険かもしれないけど、人生100年時代の今、もう少し株式比率を上げてもイイのでは?という考え方をする専門家は多いよ。
2000年の法律改正で、老齢厚生年金の支給開始年齢がそれまでの60歳から65歳に引き上げられることになりました。

昔は定年が60歳で、老後の年金生活は60歳から始まるのが普通でした。この変化が意外とアセットアロケーションにも関係してきます。
アセットアロケーションは、仕事をしなくなる定年が近くなるにつれて債券割合を増やしていくのが普通です。
| 若者 | 高齢者 | |
|---|---|---|
| リスク許容度 | 高い | 低い |
| 債券比率 | 低い | 高い |
| 株式比率 | 高い | 低い |
でも、近年の年金支給開始年齢の引き上げや平均寿命が長くなってきたことにより、40代で債券の割合を高くしてしまうと、資産を増やすチャンスを失ってしまうという考え方も増えてきています。
定年もいったん65歳で区切りはつくかもしれませんが、そこから再雇用で働き続けるケースも増えていて、さらには高齢者の雇用促進のための支援や助成金制度がどんどん生まれています。
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。

40代の私たちが高齢者になるころには、
もう70代まで仕事をするのが当たり前になっているかも…。
そうなれば40代で債券割合を50%にして守りに入りすぎると、思ったように資産が増やせず、老後資金が足りないケースも出てきてしまいます。
もちろん、高齢者が働ける場所は増えていると思いますが、実際に自分が体力的に働ける状態にあるかはわかりません。
年金の繰り下げ受給ができるぐらいの資産構築が理想
私はできれば年金の繰り下げ受給をしたいと思っています。
繰り下げによる加算額は、繰り下げをする月数に0.7%をかけて捻出され、最大で84%まで増額できます。
増額率(最大84%)= 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
途中でFIREやセミリタイアする可能性もある私の場合、もらえる年金が減ってしまうことも考慮せねばならず、その分繰り下げ受給制度を利用して、普通の年金ぐらいまで増やしたい意向です。

いろいろ考えると少なくとも50歳ぐらいまでは株式割合多めにして、資産を増やすことを第一優先にしたいです。
アセットアロケーションは定期的に見直す
40代は、まだ若く、アセットアロケーションを一度組んだからと言って、老後までそのままで良いハズがありません。
資産運用は、大体5年単位で見直したいところ。
しょっちゅう見返す必要はありませんが、5年単位でリスクを調整していく必要があります。

私は1年に1回リバランスを検討しますが、結局本当に変えるのは大体5年に1回ぐらいになっています。
あまり短期で変えすぎると、それはそれで間違った判断に結び付く可能性も。
アセットアロケーションは市場の暴落などがあって一時的にバランスが悪くなったとしても、長期で見ればそんなに大きく方針を変える必要はありません。
市場環境というよりは、自分の投資目的や生活環境の変化、リスク許容度の変化などによって大きく変わっていくものなので、定期的に見直して振り返る時間を持つのがおすすめです。

短期的な変動にまどわされず、常に長期的な視野に立って管理していきましょう。
\NISAが気になる方は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/
【合わせて読みたい】つみたてNISAをやって私が後悔したこと。ブログで語る本音と新NISAでの改善点
40代のアセットアロケーションについてのよくある質問
40代の方がアセットアロケーションを見直す際に、よくある質問をまとめました!
日本人全体のアセットアロケーションは?
40代で投資をしている人の割合はどのくらい?
一つずつ見てみましょう。
日本人全体のアセットアロケーションは?
日本銀行が定期的に発表している資金循環統計によると、日本人の金融資産のアセットアロケーションは、以下のとおり。
| 2023年9月末時点の割合 | |
|---|---|
| 現金・預金 | 52.5% |
| 債務証券 | 1.3% |
| 投資信託 | 4.8% |
| 株式等 | 12.9% |
| 保険等 | 25.4% |
| その他 | 3.2% |
預貯金の割合が50%以上を占め、その次に保険等の25%が続きます。
株式等は10%強ですが、債券はさらに小さい約1%なので、株式と債券の割合としては、株式の方が大きくなっています。

日本人はやっぱり現金が好きな国民であることに変わりがないようです…。
現金はいわゆる無リスク資産に該当し、リスクもリターンも少ない資産です。
例えばこの50%の現金資産を投資信託や株式に回すことができれば、もっと大きく資産を増やすことができるはず…。
日本人のアセットアロケーションは、世界的に見ても守りの要素が強いと言えそうです。
40代で投資をしている人の割合はどのくらい?
2021年に野村アセットマネジメントが行ったアンケートによると、40代の投資信託の保有者の割合は9.6%でした。
【投信保有者率(前年度比較)】
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| 20代 | 5.5% | 6.7% |
| 30代 | 8.0% | 9.7% |
| 40代 | 8.9% | 9.6% |
| 50代 | 11.3% | 11.4% |
| 60代 | 16.3% | 16.2% |
| 70代以上 | 20.0% | 19.0% |

実際は株式や債券、不動産投資などもあるので、投資全体だと約10%強だと考えられそうです。
気になるのは20代、30代が前年度比1%以上に増加しているのに対し、40代は0.7%しか増えていない点です。
まだ資産の増加が見込めるぎりぎりの年代の割に、投資マインドが弱いとなると、ちょっと今後が心配な結果です。
\NISAが気になる方は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/
まとめ:40代独身OLのアセットアロケーション&ポートフォリオ
今回は40代独身OLである枝豆のアセットアロケーションを大公開させていただきました。
40代でも資産を増やしたい意向が強く、かなりリスク高めなアセットアロケーションだったので、参考になる部分は少ないかもしれません。
とはいえ、人生100年時代に向けて、年齢の解釈が少しずつ変わってきているのは事実です。
今の40代は昔の40代とは明らかに異なり、まだ中堅に入ったばかり。
今の段階であまり守りに特化したアセットアロケーション&ポートフォリオにしてしまうと、老後の資産形成が十分に進まない可能性もゼロではありません。
難しいのは、アセットアロケーションに明らかな正解はないということ。
自分の資産運用の目的や家族状況、そしてリスク許容度を明確にして、自分に合ったアセットアロケーションを検討するところから始めてみてください。
それでは今日もまめまめたのしい一日を。
\米国債が気になる方は、この記事もおすすめ(*´▽`*)/