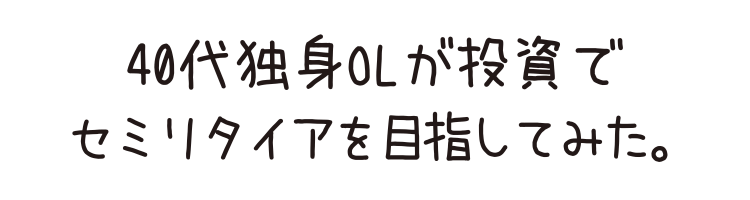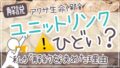セミリタイアを目指しているけど、後悔&失敗しないか心配…
経験者の体験談を参考にしたい!
今回は、こんな疑問について検証します。
▼本記事の内容
・セミリタイアした人が後悔しがちなことと失敗事例
・満足度の高いセミリタイアを実現するための対策法
ご紹介内容はあくまで個人の見解と運用実績であり、正確性や安全性を保障するものではありません。また情報提供のみを目的としており、投資、法務、税務その他のアドバイスを意図しているわけでもありません。当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。詳細はこちら
人生は、たった一度きり。いつかセミリタイアをして、自分らしい人生を送りたいー。
そんな希望を持ち、セミリタイア生活を実践する人が増えています。
「セミリタイアしてよかった!今すぐするべき」という方が多い一方で、「セミリタイアをして後悔している」とおっしゃる方もゼロではありません。

実は枝豆の父も、セミリタイア経験者です。でも、彼の場合は客観的に見れば、ちょっと失敗…。(性格上、後悔するタイプではないので、本人が「後悔」を口にしたことはないけど…笑)
今回は、そんなセミリタイアの先輩たちの生の声を集めて、対策法を整理してみました!
セミリタイアとは
そもそもセミリタイアとは、どんなライフスタイルを指すのでしょうか?

最近は、「セミリタイア」「アーリーリタイア」「FIRE」などなど、似た言葉がたくさんあってややこしいよね…。
セミリタイアは、いわゆる和製英語で、2つの言葉を組み合わせた単語です。
セミ(semi)→半分
リタイア(retire)→引退
セミリタイア=半分引退したライフスタイルのこと
「セミリタイア」は、ある程度生活できるぐらいの資産を先に貯めることを前提としています。
そして、食べていくための仕事(ライスワーク)を減らし、好きなこと(仕事、社会貢献活動、その他…)に使える時間を増やすライフスタイルを指します。
サラリーマンとして会社で働くことをやめ、フリーランスや自営業で、好きな時間に好きなだけ仕事をするケースが多いようです。
\枝豆もセミリタイア目指してます!セミリタイアのための詳しい投資方針はこちら(*´▽`*)/
【合わせて読みたい】
わたしの投資運用方針と資産目標
完全リタイアとの違い
セミリタイアと比較される言葉に、完全リタイアがあります。
完全リタイア(またはリタイア)は、いわゆる「引退」や「退職」をさし、その後は一切仕事を辞めることを指しています。

ただし、体が動かないお年寄りでない限りは、完全リタイア後も何かしらの社会貢献活動をすることが多く…最近はこの違いがあいまいな気もしますね。
アーリーリタイアとの違い
アーリーリタイアは、セミリタイアとは違い、海外でも使われる「リタイアアーリー」がもとになっている言葉です。
リタイア(retire)→引退
アーリー(Early)→早期
単純に早く引退することを指し、セミリタイアはアーリーリタイアの一種であると考えられています。
FIREとの違い
FIREは、アーリーリタイアの一種です。
経済的に自立したアーリーリタイア(早期退職)を指しています。
ファイナンシャル(Financial)→経済
インディペンデンス(Independence)→自立
リタイア(retire)→引退
アーリー(Early)→早期
経済的に自立した状態=資産の運用利回りで生活費がまかなえ、資産が減らない状態を指しているため、セミリタイアよりもさらに条件が厳しい言葉だといえるでしょう。
セミリタイアは、資産が多少減ったとしても仕事で賄っていくことを前提にしているので、FIREよりゆるい定義になりますが、最近はFIREにもいろんな種類があり、定義が似てきているのはたしかなようです。
参考までにFIREの種類を紹介すると、以下のとおり。
ファットFIRE
=リタイア後も豊かな生活を送ることができるFIRE
リーンFIRE
=リタイヤ後は最小限な生活を送るミニマリスト的FIRE
バリスタFIRE
=金融資産から得られる不労所得とパートタイムの仕事で半分ずつ賄うFIRE
コーストFIRE
=FIRE前と同じ労働を続け、金融資産には手をつけず、さらに資産を増やしていくFIRE

厳密には違うのかもしれませんが、バリスタFIREがセミリタイアに近そうです。ただ「FIRE」という言葉は、人によって解釈が違うので安易に使うと誤解が生じそうですね…。
経験者は語る!セミリタイアをした人が後悔しがちなこと&失敗事例
セミリタイアをした人が後悔しがちなことと、失敗事例をまとめると、以下の7つに集約できそうです。
お金が足りず後悔する
想像していたセミリタイア生活と違って後悔する
社会的な信用が下がって後悔する
失敗した後の職探し・再就職が難しくて後悔する
人との関わりが希薄になり、後悔する
番外編:なぜもっと早くセミリタイアしなかったのかと後悔する
番外編:移住先の田舎に馴染めず後悔する
一つずつ見ていきましょう。

枝豆の父の経験も、経験談としてご紹介していきます(*´▽`*)
お金が足りず後悔する
セミリタイアする上でやっぱり重要なのは、お金です。
お金が足りず、セミリタイアをしなければよかったと後悔する人も多いみたい。

やっぱりお金は大事です…!
セミリタイアをするときには、最低でも日々の生活費が金融資産からの所得で賄えるようになってからするのがおすすめ。
資産所得>生活費
でないと、枝豆の両親のように、生活費自体がままならなくなる可能性があるからです。

もともと計画性がなく、それが理由で何度も仕事上のトラブルが生じている枝豆の両親ですが、彼らのセミリタイアの場合は、こんなことが…。
・セミリタイアと同時に、都心のマンションを売り、田舎の一軒家をに引っ越し
・枝豆の父は、一軒家で古民家カフェを営もうと計画
・実際に引っ越してみたら、一軒家の水回りが古く、そのまま使うのは危険すぎることが判明
・カフェ経営のリフォーム代を自宅の水回りのリフォーム代に充てるため、カフェ経営を断念
・期待していた仕事&収入が得られず、生活費も節約が必要に

うちの両親が計画性ゼロなのはあるあるで、娘としては、あーまたやってる…笑 なのですが、まぁ、普通笑いごとじゃないよね…
お金に関しては、どんなトラブルがあるかわからないのが正直なところ。
セミリタイアは、少なくとも「資産所得>生活費」になってから。
多少のトラブルがあっても、生活自体は変わらないことを前提にした計画を立てることが重要です。
・住居/車などの設備故障などの予定外の出費
・怪我や病気などの労働収入の減額
・インフレなどの外部環境の変化 など

計画を入念にしても、怪我や病気などのトラブルに見舞われることもあるので、もちろんいろんなケースを想定する必要があります。
想像していたセミリタイア生活と違って後悔する
実際にセミリタイアしてみたら、思っていた生活と違って後悔することもあります。

あと、想像と違ったというより「飽きた」という方が意外と多いことがわかりました。
3年前にセミリタイアしてニート生活が板についてしまい、現在絶賛引きこもりニートだがいい加減この生活にも飽きた。誰かボクを時給で雇ってくれませんか?どんな仕事でも頂く時給より稼ぐと思います。あ、朝の早起きだけは苦手です。
引用:Xより
30代前半で会社を売り、20億を手にして舞い上がり、セミリタイアして世界中遊び回った。だけど、1カ月で飽きた。そこに行けば美しいし楽しいんだけど。嫌になり死を考え、山中で長い遺書を書いていて、気が付いた。今から生まれ直して、やり直そうと」(ある友人)人は飽きる、だから進化が必要です。
引用:Xより
特に最近は、セミリタイア生活が流行っているというのもあって、自分の性格や理想に合っていないことも多いよう。
なんとなく「仕事を辞めたい」「違うライフスタイルを送りたい」と夢見ているうちはよいのですが、自分の性格にセミリタイアライフが合っているかをちゃんと見極めることが大事なようです。

枝豆の両親の場合は、結局カフェ経営ができず、予定していたセミリタイア生活とは全く違うものになりました。
予定していたセミリタイア生活
父:カフェ経営
母:月4~5回だけ都心で単発のお仕事、その他は父のカフェをお手伝い
実際のセミリタイア生活
父:とくにやることなし、年も年なのでのんびり引退生活
母:普通に都心で単発のお仕事

ぜんぜん想像と違う生活となりました…父は目標を失ってしばらく元気がなかったです…そりゃそうよね…
社会的な信用が下がって後悔する
セミリタイアすると、社会的な信用がなくなり、後悔する人も多くいます。

枝豆の父は、もともと自営業だったのであまり関係がありませんが、一般的にはとてもよくあることなのだそう。

え…これは普通にショック…。ひどいですね…。
もちろん個々の事情によりますが、フリーランスや自営業の友人から聞く話を総合しても、社会的な信用がないことで余計な出費が生じたり、計画通りの仕事ができないということは多いようです。
・クレジットカードが作りにくい
・賃貸物件が借りにくい
・住宅ローン審査が厳しくなる(=現金を多く持たないといけない)
・不動産投資経営がしにくい(=投資のレバレッジが効きにくいため損しやすい)

不動産投資をしている私も、実際に不動産やさんからはっきりと「サラリーマンのうちじゃないと、物件増やせませんよ」と言われています。
不動産投資事業はしにくくなる可能性が高いので、よほど資産額が大きくない限りは、セミリタイアをする前に不動産を購入しておいた方が良いかもしれません。
不動産の会に参加させてもらい、新しい可能性を感じました。
と同時にセミリタイアしたの若干後悔😌←
それでも自分の中で不動産というものは確実に私が描く未来像に近づけてくれる存在であることを認識できた!だから今後、私では難しい部分を彼に補ってもらいながら2人で不動産投資頑張る💪
引用:Xより

不動産投資に興味がある方は、ご注意を!
Youtuberさんもよくおっしゃっていますが、賃貸物件を借りたいときも、社会的信用の低さが不利になる可能性があるので、注意が必要です。
YouTuberは家を借りられないって話、ガチだったんだなぁ……(審査落ちなう)
引用:Xより
YouTuberは家借りられない!!!先日引っ越す時、私の名義では家借りられませんでした。しかし、大企業に勤めている妻の名義だと2秒でOK。悲しいですが、これが現実!もっと信用を積み重ねられるような活動をしていきます!!!
引用:Xより
でも、これも実はお金が解決してくれる問題。セミリタイア時の資産額が大きければ、そこまで心配することはないかもしれません。
無職だと部屋を借りられない?意外とそうでも無かったです。1発で賃貸の審査が通りました。無職でも残高があればどうにかなるな。
引用:Xより

いろんなパターンがありますね…!資産額や場所など、いろいろなケースによって違いがありそうです。少なくともわたしは、セミリタイア前にローンを組んでおこうと思っています。
失敗した後の職探し・再就職が難しくて後悔する
セミリタイアすると、職探し・再就職が難しくて後悔することもあるようです。
特に若くしてセミリタイアをした場合、「最悪失敗したら就職すればよい」と考える人も多いと思います。
しかし、一度リタイアすると、ライバルと比較された場合に中断されたキャリアが仇となり、再就職が難しくなるケースがあるようです。

履歴書の空白が、「すぐやめてしまうかも…」と思われやすいみたい…。特に40代以降の正社員の再就職は、セミリタイアでなくても専門的なスキルがないと難しいと言われます。
セミリタイア体験談について調べてると
・50代セミリタイア⇒再就職出来ない等苦労してる
・30代中資産セミリタイア⇒副業で結構稼いでる
・30代低資産セミリタイア⇒仙人生活
このパターンが多い気がする
引用:Xより

結局、セミリタイアしてみないとわからないけど、セミリタイアを決断した時点でそれなりの覚悟は持っておいた方がよさそうです。
また正社員として働くよりも、金融資産を使って利益を得る方法や副業などを極めるほうが、現実的かもしれません。
人との関わりが希薄になり、後悔する
セミリタイアすると、人との関わりが希薄になり、後悔する人もいます。
セミリタイア前は会社勤めをしていて、毎日新しいプロジェクトに出入りしていて、いろんな人との出会いが定期的にあった場合、基本的には家にいるセミリタイア後の生活は、違和感があるケースも多いでしょう。
むしろ、人との関わりがストレスになる方にとっては、こんなにうれしいことはないんだけど…。これって、セミリタイア生活が合うかどうかの重要なポイントである気がします。

わたしは数日間ひとりでいても、好きな場所で、ブログを書いたり、読書してるだけで幸せ感じられるタイプなので、おそらく大丈夫かなと思っています…笑 甘い??
会話をするのは家族だけ、という日が、かなり増えました。
正直なところ、人とのコミュニケーション量が減ったので、つまらないなと思うこともよくあります。
引用:まさどん不動産
政治界隈をセミリタイアしたことは全く後悔してないが、惜しむらくは仲良くさせていただいていた政治垢の皆さんとの交流も減ったことだろうか まあ主に政治ネタで絡んでいた以上、仕方のないことではあるが笑 他のネタでツイされてたら、たまにはお邪魔してみますかね
引用:Xより
さらに家にいる時間が増えて、家族との仲が悪くなるケースも。
いつも仲良しにみえる「アラサー夫婦の沖縄移住セミリタイア生活」さんも、こんなつぶやきをされてました。
ぶっちゃけ夫婦なら二人で沖縄生活を十分楽しめると思ってました。むしろ、妻は人見知りで人付き合いが苦手なタイプなので、ひっそりと生活するイメージを持ってました。
ただ1年経って、今では毎週・毎月会うような友人もでき、沖縄生活をより楽しめています。
友人がいなければ畑をしたり、釣りをしたり、ヤギを食べる機会もなかったでしょう。
そして夫婦二人でずっと居るどうしても煮詰まっちゃうときがあるんですよね。
(熟年離婚する原因がわかった気がします。笑)
引用:Xより

人間関係って、やっぱりとても難しい…
番外編:なぜもっと早くセミリタイアしなかったのかと後悔する
意外と多いのが、セミリタイア自体には一切後悔がなく、なぜもっと早くセミリタイアしなかったのか、自分の選択の遅さに後悔している人がいます。

セミリタイアライフがすごくマッチした人のケースですね!こういう方も結構多いです。
もっと早くセミリタイアすべきだったと語る人が、なぜそう思っているのかをまとめると、以下のとおり。
・年をとればとるほど、楽しいセミリタイア時間が少なくなるから
・年をとればとるほど、体力と気力が落ちて、時間があってもできることが減るから
・海外生活しやすい制度に年齢制限がある場合も多いから

時間や体力はもちろんそうだけど、セミリタイア中に使いたい制度に年齢制限があるというのは、盲点だったという方も多いのでは?
例えば、比較的自由に海外生活を体験できるビザとして有名な、「ワーキングホリデービザ」。
国によって制度の詳細は異なりますが、「ワーキングホリデービザ」の年齢制限は、18歳から30歳が一般的です。
20代のうちにセミリタイアすれば、ワーキングホリデービザで気楽に海外に行けたのに…と後悔する方も多いみたい。
さらに、年齢制限とは関係がなくても、年々取得難易度が高まっているビザもあります。
例えば、2003年に開始された、タイ国営の長期滞在プログラム「タイランドエリート」は、2023年に廃止となりました。
もちろん、海外の長期滞在プログラムは日々変化しており、新しいプログラムもどんどん生まれているので、早ければ早いほど良いというわけではありませんが、海外でのセミリタイアを視野に入れている方は、常に新しい情報をつかんでおく必要はありそうです。

特に30~40代の人が海外で生活したい場合、ワーホリも使えないし、リタイアメントビザも使えないし…ビザ問題は大きそうですね。定期的な情報収集がおすすめです。
番外編:移住先の田舎に馴染めず後悔する
セミリタイア自体の後悔ではありませんが、セミリタイアと同時に田舎に住居を構え、そこでなじめなくて後悔する人は少なくないようです。

枝豆の両親も、最初はかなり戸惑った様子でした…。ご近所さんづきあいも都心とはかなり違うもんね…。
もちろん、田舎だからなじめないというわけではなく、引っ越ししたら、ご近所さんと合わなかったというのはよくあるはなし。

わたしがオーナーをしている不動産でも、先日隣人トラブルがあって、結構大変でした…。
田舎だろうと、都会だろと、マンションだろうと、一軒家だろうと、隣人トラブルは避けられません。
(よく「隣人ガチャ」と言われるけど、まじでそれ!)
お金があれば、引っ越しもしやすいので…やっぱりセミリタイアをする時は余裕を持った資金計画をしたいなと思いました…

わたしはやっぱり田舎より、ある程度ほっといてもらえる都会のほうが合っている気がするなぁ・・・今のところは、セミリタイア後も田舎暮らしの予定はないです。
経験談に学ぶ!セミリタイアで後悔しないための対策法
これまでの経験談を踏まえ、セミリタイアで後悔しないための対策法を整理してみましょう。
具体的なポイントは、以下のとおり。
生活のイメージを具体的に整理する
セミリタイア後の収入・支出を計算する
家庭と仕事以外のネットワークをつくる
ケガや病気リスクへの備えをする
投資の勉強や基盤づくりをする
一つずつ見ていきましょう。
生活のイメージを具体的に整理する
セミリタイア生活を後悔しないためには、理想とする生活のイメージを具体化し、それが可能かどうかじっくり調査した上で、計画を立てることです。
住む場所はどこなのか?
毎日どんなことをするのか?
毎日どのくらい働くのか?
働く目的や意味は変化する?
セミリタイア後の投資戦略は?
生活費や必要経費はどのくらい?
コミュニケーションはどんな人と?どの程度?
予想できるアクシデントにはどんなものがある?

枝豆の両親は、このあたりの計画が、「田舎で古民家カフェやりたい!」だけだったのが、セミリタイア失敗の原因だと思われます。良い子はマネしないでね。笑
あこがれだけで、「田舎に住みたい」「古民家カフェを経営したい」と考えるのは、ちょっと危険。
本当にやりたいなら、セミリタイア後の生活を疑似体験するために、実際に短期間田舎に住んでみたり、カフェでアルバイトしてみたりしながら、自分のイメージと相違ないかひとつひとつ確認していく作業が必要でしょう。

想像と現実のギャップがなるべくなくなるように行動できるのが理想!わたしもセミリタイア前に必ず疑似体験しようと思ってます。
セミリタイアは、必ずしも自分に向いているとは限りません。
なかには、セミリタイアが向いていない人もいるので、自分の向き・不向きを理解せずに行動してしまうと後悔することになります。
自由な時間が増えるセミリタイアは、そもそも自由な時間に不安を覚えてしまう人は向いていません。
また、自ら興味のあることを見つけることができない人も、あまり向いていないと思います。
ずっとサラリーマンとして仕事をしてきた人は、ゼロ地点からやりたいことや好きなことを見つけるのがニガテな人も多いので、セミリタイア生活が意外とストレスになる可能性も。
夢中になれるものを、自分で見つけるのは容易ではありません。依頼を受けて仕事をすることのほうが楽しかったと後悔する人もいるので、くれぐれも衝動的にセミリタイアするのはやめましょう。

私は15年以上サラリーマンしながら、フリーランスをしてきたので、どちらのタイプの方とも交流があるのですが、やっぱりしあわせの質ってみんな違うなぁと思います。個人的な印象ですが、フリーランスっぽい動きをする方のほうが、セミリタイア向きの人が多そうです…。
地方移住を検討される場合は、具体的なイメージづくりのために短期間住んでみる、または地方アンバサダーになってみる方法もあります。

うーん…やっぱり10万円/月はかんたんではないんだなぁ…。
例1:ワーケーションアンバサダー募集(沖縄県)
アンバサダーになるメリット:
一流ホテルや会員制施設の宿泊が無料
コワーキングスペースの利用が無料
アクティビティ・イベントの優待特典 など
.jpg?resize=1024%2C451&ssl=1)
例2:未来ワーク福島アンバサダー募集(福島県)
アンバサダーになるメリット:
Amazonギフトカード 42,000円分進呈
SNSなどの発信活動フォロー など
.jpg?resize=1024%2C452&ssl=1)

最初はこういう制度を使ってみて地方を知るのもよさそう…!セミリタイアが具体的になってきたら、わたしも応募してみたいと思っています。
セミリタイア後の収入・支出を計算する
生活の具体的なイメージができたら、セミリタイア後の収入・支出を計算してみましょう。
少なくとも資産所得で生活費が賄えるのが、最低限の基本です。
資産所得>生活費

なにかしらの事情で労働ができなくなる可能性もゼロではありませんから…!
住む場所が変わる場合は、物価も変わり、支出の項目や種類も大きく変化する可能性があります。
あくまで今の生活基準で考えず、セミリタイア後の生活を具体的にイメージして、新たな気持ちで生活費を見積もりましょう。
生活費はどのくらいかかるのか?
いざという時の備えはどのくらい必要か?
老後資金はどのくらい必要か?
労働収入はどのくらい期待できるのか?
金融資産からの利益はどのくらい期待できるのか?
資産運用から得られる不労所得はどのくらいか?

セミリタイアすることで、そのままサラリーマン生活を続ける場合よりも将来もらえる年金は少なくなります。その辺も抜けもれなくシミュレーションしたいよね…。
お金に関しては、ひとりひとりの考え方がかなり違うので、正解はありません。
自分が不安を感じず、セミリタイアライフを安心して継続できるなら、いくらでもセミリタイアは可能なのです。
僕は400万円という低資産でセミリタイアしたけど、低資産リタイアで後悔した事が全くない。株式のリターンを考えると、将来は今よりも必ずお金持ちになっているし、毎日が驚くほど楽に楽しく生きている。それに同じ考えの仲間も出来て、応援してくれる人達も居る。本当に最高じゃないか。お金のあるなしは関係ない
引用:Xより

素敵な考え方!ほんとそうよなぁ…!わたしはお金がないと不安になっちゃう自分を知っているので、予算多めのセミリタイアを目指します…!
セミリタイアの具体的なプランを考える上で、特に田舎暮らしなども検討する方は、総務省が公表している家計調査データも参考にしてみてください。
家計調査(家計収支編) 調査結果|総務省
https://www.stat.go.jp/data/kakei/rank/singleyear.html
家庭と仕事以外のネットワークをつくる
セミリタイアを楽しいものにするコツは、やっぱりコミュニケーション力を鍛えるのが大事だと思います。

後悔している人の多くが、人とのつながりを挙げているってことは、さすがにひとり大好きな私もちょっと心配になる…
特に私のような独身セミリタイア民は、今から仕事以外の人と積極的にかかわりを持ち、SNSやオンラインサロンなども積極的に利用していくのがよさそうです。
さらに、ご家族がいらっしゃる方も油断は禁物!笑
セミリタイアしたら夫婦仲が悪くなったというケースは、本当に多いので、それぞれが自立して楽しめるように、どんな家族構成の方も例外なく、コミュニケーション力を磨いていきましょう。
ケガや病気リスクへの備えをする
セミリタイアでお金以外に失敗の原因があるとすると、コワいのはケガや病気を患ってしまうことです。
サラリーマンとして働いていれば、突然のケガや病気で会社を休むことになっても手厚い保障が受けられます。

サラリーマンの人は意外と気が付いてないけど、ほんと休業補償給付ってすごいんです。
労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき 、 その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者休業給付(複数業務要因災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
休業補償給付、休業給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)× 休業日数
引用:労災保険資料|厚生労働省
・休業4日目から最長で1年6ヶ月まで、傷病手当が給付される
・金額は、給付基礎日額の60%+20%
しかし、セミリタイア後は、このような手厚い保障はないため、サラリーマンとして働いている時もさらに健康に気を使う必要があり、人によってはケガや病気リスクへの備えが必要になります。

病気にならないこと、ケガをしないことがすごく大事になるので、なによりも生活習慣を整えることが大事!
投資の勉強や基盤づくりをする
セミリタイアで後悔しないためには、何かのトラブルがあったとしても、自分で解決できる能力が必要です。
特に、いざとなったら自分で必要なお金を作れるという自信は、セミリタイアライフを充実したものにしてくれるはず。
それも、労働収入ではあまり意味がなく、自分の代わりに働いてくれる不動産資産や金融資産を作れる投資スキルを身につけたいところ。

資産運用スキルに関しては、わたしも常に勉強中…。そういった意味でも、比較的大きな資産を作ってからセミリタイアするほうが私は安心です。
不動産投資
=小さい規模から始めるなら、サラリーマン向き
=アパートやマンション、一軒家といった不動産を購入し、賃貸で収入を得る
=年々買いやすい物件は値段が高騰ぎみなので、今から始めるならリフォームスキルを身につけるなどの工夫が必要
=相続対策や所得税・住民税の節税対策にも役立つ
株式投資
=まずは新NISA制度を利用して、コツコツ小さい規模から始められる
=利益には売却益(キャピタルゲイン)、配当金(インカムゲイン)、株主優待の3種がある
=ペーパー資産なので、管理コストがかからず、比較的スタート時のハードルは低い
まとめ
今回はセミリタイアをした人が後悔しがちなこと&失敗事例と対策法をまとめてみました。
セミリタイアをした人が後悔しがちなことを整理すると、以下の7つです。
お金が足りず後悔する
想像していたセミリタイア生活と違って後悔する
社会的な信用が下がって後悔する
失敗した後の職探し・再就職が難しくて後悔する
人との関わりが希薄になり、後悔する
番外編:なぜもっと早くセミリタイアしなかったのかと後悔する
番外編:移住先の田舎に馴染めず後悔する
お金が足りずに後悔するのは想像しやすいですが、同じくらい意外とお金はかからないので、もっと早くセミリタイアすればよかったと考える人が多いことに驚きました。
要は、セミリタイアに必要金額は関係なく、セミリタイア後の生活をどれだけ具体的に想像できていて、どれだけ計画・準備ができているかが成功・失敗を分けるキモであることがわかります。
人によってはそもそもセミリタイアが合わないケースもありますし、資産を多く準備する必要がないケースもあり得ます。
セミリタイア生活が気になる人は、まず自分が理想とする生活がどんなものであるか、具体的にイメージし、可能であれば体験してみることからはじめるのがおすすめです。
セミリタイアを目指す方は、ぜひ参考にしてみてください。
それでは今日も、まめまめたのしい一日を。
\詳しい枝豆の投資方針はこの記事を読んでみてね(*´▽`*)/
【合わせて読みたい】
わたしの投資運用方針と資産目標